
炎獄の楔~凄惨を食むならば
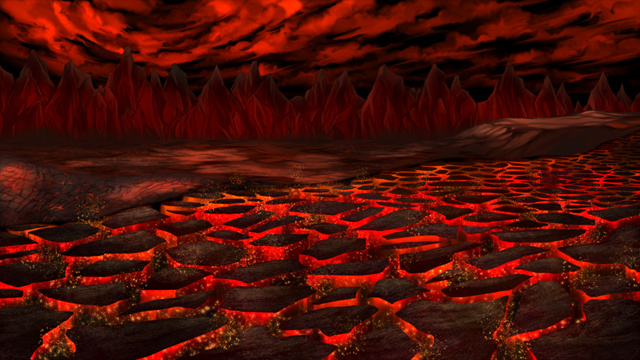
●炎獄の畔
「何はともあれ、垓王牙大戦の戦いに参加した皆はお疲れさま。結果は残念なものになったけれど……最後の最後まで諦めずに戦ったからこそ、今この現実に向き合えるのだとも言えるもの」
小鳥居・鞠花(大学生エクスブレイン・dn0083)は僅かに吐息を噛む。視線は真直ぐ揺るがぬままだ。立ち向かうべき『現実』を詳らかにするため、鞠花はあくまで冷静に資料を紐解く。
「ガイオウガは回復のために、日本各地の地脈からガイオウガの力を集めようとしているの。仮に日本中のガイオウガの力が、復活したガイオウガの元に集約されてしまえば……最盛期の力を取り戻してしまうに違いないわ」
その結果どのような事が起こり得るか、それを想像出来ぬ灼滅者達ではあるまい。そう理解しているから、再び顔を上げて宣言する。
「絶対に阻止しなきゃいけないわ。だから皆には、日本各地の地脈を守るガイオウガの力の化身――強力なイフリートの灼滅をお願いしたいのよ」
灼滅者達は日本各地の地脈に散り、それらのイフリートと対峙する事になる。が、喩えるならばガイオウガが王であれば地脈を守るイフリートは地方領主のようなもの、その周囲には更に数多のイフリートが防護を固めているだろう。
「でも、このイフリート達は垓王牙大戦で救出に成功した『協調するガイオウガの意志』の力で戦闘の意志を無くして、無力化する事が可能になっているわ。これも皆の健闘の賜物ね。とはいえこの意志の力も、強力なイフリート自体には影響を及ぼせないの。強力なイフリートについては、灼滅者の皆が撃破する必要があるわ」
それに戦闘の意志を抑えるためには、イフリートの戦意を刺激しないように、少数精鋭で戦いを挑む必要がある。強敵相手に少人数で立ち向かわなければならない現状を鑑みると、かなり危険な任務としか言いようがない。
「状況次第では闇堕ちをしなくちゃ勝てないかもしれない……とはいえあたしは欲張りだから、皆に無事に帰ってきて欲しいわ。本当よ」
困ったように笑ったなら、鞠花はファイルのページを進める。
相手取るイフリートは黒い焔を纏う黒豹の姿らしい。名は『炎駒』、エンクと呼ぶらしい。王者の風格漂わせる面持ちはまさに強者、覇気と頭脳を兼ね備えているため、怖気づく事も油断する事もあり得ないだろう。むしろ地の利は敵にあるのだ、炎駒のほうが灼滅者を殲滅せんと狩る立場と言えるかもしれない。甘い考えでは全滅させられてしまうかもしれないほどの強さだ。
すなわち、相手と仲間の実力をいかに冷静に分析し、その上で敵に先んじるよう手を尽くさねば勝ち目は見出せぬという事。僅かな隙、些細な油断が致命的な傷となり得るのだと鞠花はいつになく厳かに告げた。
「炎駒のポジションはキャスター。縛霊手とエアシューズ、ダイダロスベルトに相当する技を駆使してくると考えられるわ。勿論イフリートだからファイアブラッドのものも。今回に限って言えばすべての能力値が極めて高いから、弱点を狙うという戦法が取りづらいのが悩ましいかしら。体力もあるからものすごくタフよ」
戦闘場所は地下の空洞、地脈周辺。そこまでの誘導については協調の意志を持つイフリートが担ってくれるだろう。その上で取り巻きのイフリートの無力化に力を尽くしてくれるので、灼滅者達は炎駒との闘いに専念出来るだろう。
洞窟内では崩落等の危険は特にないが、外の光は一切入ってこない。視界には留意する必要がある。足元にも気を配らなければ文字通り足元を掬われかねない。
「今回の敵は、無傷での勝利は難しい強敵なのは間違いないわ。でも怖気づいてなんかいられないの。この敵に打ち勝たなきゃ、復活したガイオウガを止める事は不可能になってしまう」
ファイルを閉じる。集まった灼滅者達の面立ちを見渡す。
目を逸らさずに、鞠花は不敵に笑んで送り出す。
「行ってらっしゃい、頼んだわよ!」
皆の勝利と無事とを祈っているから。そう、強い信頼を灼滅者達に寄せて。
| 参加者 | |
|---|---|
 西羽・沙季(風舞う陽光・d00008) |
 科戸・日方(大学生自転車乗り・d00353) |
 鹿野・小太郎(雪冤・d00795) |
 鳴神・千代(ブルースピネル・d05646) |
 檮木・櫂(緋蝶・d10945) |
 東屋・紫王(風見の獣・d12878) |
 野乃・御伽(アクロファイア・d15646) |
 ユメ・リントヴルム(竜胆の夢・d23700) |
■リプレイ
●壱
足場を確認しつつ、灼滅者達は洞窟を進む。各々が用意した登山靴が頼もしい。
奥から焼き付く熱風と凄まじい威圧を感じるが、周囲は現状落ち着いている。『協調するガイオウガの意志』が抑えていてくれているからだろう。
足元を照明が照らしている。灼滅者達が共通のショップで購入したと思しきLED投光器は充電式で、複数人が用意した事もあって光量は十分。
「随分歩いたね。そろそろお出ましかな」
「……ええ。いるわ、この先に」
伸びる光の向こうを見遣る。鳴神・千代(ブルースピネル・d05646)が霊犬の千代菊の背を撫でながら唇を引き結べば、檮木・櫂(緋蝶・d10945)が紅色の瞳を眇めながら、呟いた。
さて、これだけ明るければ相手も潜入に気づいているだろう。そもそも隠密行動をしているわけではない。今自分達が立っている広間はどうやらかなり開けているようで、歩いて来た道ほどには地面も荒くはないようだ。
投光器のいくつかを自陣の背を照らすように設置したなら、進行方向を明るく浮かび上がらせる事に成功した。
――戦うのに、支障はあるまい。
仲間内で視線を交わしたなら、頷いた。
ユメ・リントヴルム(竜胆の夢・d23700)は毅然と顔を上げ、空洞の奥へと向き直った。深呼吸の後、声を上げる。
「炎駒、ボク達はキミと戦いに来たんだ。正々堂々、挑戦を受けたらどうだい?」
張り詰めた空気に短く息を噛んだ。緊張が場を支配する中、後押しするかのように鹿野・小太郎(雪冤・d00795)が告げる。
「……そこでしか戦えないのか。ここまで狩りに来いよ、そう簡単には負けないから」
声音は硬質で落ち着いたものだ。譲らぬ芯を感じさせるその声が響いた、刹那。
低い唸り声は焔の気配。
しなやかな黒が歩み寄る。その闇色は力量に満ち溢れているが故の重厚感と威圧感で染まっていた。黒い炎を纏った堂々とした居住まいの一頭の豹。
炎駒だ。
誰もが瞬時に把握する。大口を叩いたからには手応えがあるのだろうな。そう言っているかのような鋭い眼光。科戸・日方(大学生自転車乗り・d00353)は矜持を支えに、きつく炎駒を睨み付ける。
「炎駒を倒す為に来たんだ、倒す目がある限り退かねぇ」
それは決意の表れ。野乃・御伽(アクロファイア・d15646)も同感だと浅く顎を引いた。それぞれが己の役割分担に則り立ち位置を定める最中、最後尾で殲術道具を構える西羽・沙季(風舞う陽光・d00008)の表情は硬い。
ここで倒さないともっと被害が出る。
だから絶対に諦めない。
大切な人と肩と並べるにしてはあまりに剣呑とした雰囲気だけれど、その心強さたるや計り知れない。東屋・紫王(風見の獣・d12878)はユメを庇える距離を確保しながら、炎駒を真直ぐに見据える。
「……じゃあ、いこうか」
一歩、踏みしめる。
それが開戦の合図となった。
●弐
炎駒が吼える。
力量差故か先んじたのは敵のほう、生み出したのは荒れ狂う風、それに黒色が宿るのを見た者はいるか。後方に陣取る灼滅者達を囲い込んだかと思えば、真空の刃が躍る。
響くは、肉を裂く音。
「ぐっ……!」
鮮血が散った。複数人を巻き込む技にしては傷が深い。神経を削っていくのか、痺れが手足を蝕んでいく。
「あ、ありがと……!」
ユメの前で身を呈したのは千代菊、だが防御に徹しているはずの霊犬ですらその傷は浅くない。千代は俄かに不安を抱える。大丈夫か、本当に勝てるのだろうか。
「とても強い相手だけど、ここで何としてでも食い止めないと……だよね」
首を横に振り不安を振り払う。毅然と前を向く。その横顔を視界に入れた小太郎が馳せた。こんな傷で臆してなどいられない。
足に宿すは流星の煌めきと大地の重力。一足飛びに懐に滑り込めば蹴り上げる。咄嗟に身を躱した炎駒の背後を取ったのは紫王だ。
「まずは一手、刻む――!」
後足を捉えた。まずは機動力を削ぐ事が肝要、そのため狙い澄ませて抉る事からと刃を振るう。
「!」
後方へ飛び退く。ユメが真っ先にその曇った表情に気づいた。
「紫王、どしたの」
「いや。……想像以上に、堅い。物理的にね。これは骨が折れそうだ」
攻撃も防御も、一筋縄ではいかないと痛感する。その声を耳で拾った櫂は表情を曇らせながらも、毅然と前を向いた。
駆ける。流星の蹴撃を振り抜くも、炎駒は巨体に似合わぬ俊敏さで回避した。圧倒的な実力からくる周辺視野の広さは相当なものなのだろう。後追いしたユメの攻撃は確かに届いたものの、相手は顔色一つ変えていない。
御伽はやや眉間に皺を寄せつつ、生み出した雷を掌で丁寧に転がす。
「穿つ!!」
洞窟に迸る閃光が獣を追駆する。背筋を貫けば轟音が響いた。火力担当としての御伽の攻撃も相手に当たらなければ意味がない。彼のサイキックの選択は妥当だったと言えるだろう。
少しずつでも削っていけば、いつか必ず。そう思わせる雷光は誰の気持ちもを前向きにする。
「そうとなれば今は少しでも傷を塞がないとな!」
「勿論、絶対誰も倒れさせないよ!」
日方が翳すは傷を癒し耐性も齎す黄色標識、千代が手繰るは災いを解いていく癒しの風。重ねたならば受けた傷も徐々に和らいでいく。そこに沙季も黄色い標識を掲げ、更に手厚い治癒と浄化が行き届いていく。
だが。
「……えっ」
沙季の背筋に悪寒が走る。獣の眼光が自分を射抜いている。
護り手の合間を縫い、炎駒が腕を振り翳した。疾走するは黒き炎の弾丸。炎だと理解出来たのは、沙季の鳩尾に直撃した衝撃が一際、高く燃え上がったためだ。焦げ付く空気はそれそのものが苦い。
「くは、っ……!」
「西羽さん!」
上半身が大きく投げ出される。沙季の背が地面に落ちる前に、咄嗟に小太郎が支える。傷が深い。かろうじて意識は保っているようだが、二発食らえば気絶しかねないほどの威力。
「……西羽さんを狙った。つまり、彼女が癒し手だと把握して攻撃してきたのか」
小太郎が奥歯を噛む。初手で灼滅者達がどのように動くか、様子を窺っていたに違いない。その上で最も大きい回復量を動かし得る癒し手を確実に狙ってきた。逆の立場だったら自分達だってそうするかもしれない。
誰もが目まぐるしく動く戦場では、特に意識していない限りは護り手も常に庇えるとは限らない。
護り手で唯一、相手の出方を窺って護り方を工夫する旨考えていた日方が唇を引き結んだ。沙季が漸う立ち上がったのを確認し、小太郎と日方は真剣に頷き合う。櫂と千代、千代菊にも回復手や体力が劣る者から狙われる旨、端的に伝える。
「戦うのが怖くない訳がない。でも、誰かがやらなきゃもっとヒドイ事になる」
焦っては敵の思うつぼだ。深呼吸をして、日方は炎駒に向き直る。
「誰も失わせたりしない」
拳を握る。
絶対に退いたりしない。決意を静かに、湛える。
●参
一進一退。
言葉にすれば単純だが、灼滅者達は炎駒がいかに手強いかを身をもって知る事になる。
回避率を下げるために機動力を落としても、炎駒は浄化の炎を纏い穢れを落としていく。前衛の体力を根こそぎ奪うほどの一撃には黒き焔が纏わりついて、延焼を広げていくのが面倒だ。鋭い爪で近列を抉り払う攻撃は、強化を施していた場合、それごと切り裂き霧散させていく。
だが灼滅者達とて食らいつくのを諦めない。
重ねた攻撃は決して無駄じゃない。
「食らってられるかよ!」
粘着質に後列を削ってくる獣の一撃を、日方は射線上に身体を張って食い止める。直撃を免れるよう力づくで跳ね飛ばすが、受けた衝撃は馬鹿にできるものではない。呼吸が荒い。膝をつく。けれどまだ倒れたりしない。
沙季と千代菊が既に倒れてしまった事もあり、他の面々が回復を担わなければならなかった。
櫂は流れる水の波紋が描かれる淡青の帯を翻す。帯を加護齎す鎧と化し、日方の体を覆っていく。攻撃に転ずるほど回復体制に余裕はなく、櫂は歯がゆさに唇を噛んだ。
「誰かを守ったり人助けなんて柄じゃない。昔は失うのが怖くて人を拒絶し孤独だった。……だけど今は違う。守りたいモノが沢山出来た」
――『仲間』を守れる力が欲しい!
強い願い。癒しの水の如き力は二重となり、傷口を鮮やかに塞いでいく。小太郎は目礼したなら、拳に魔力を収縮させる。
体に添う全てが力。
紡いだ縁が標。
心の芯は、揺るぎない。
「――行け!!」
魔法弾が螺旋を描いて飛ぶ。炎駒の顎下を捉えて鋭く抉ったならば、麻痺を齎す魔力の火花が迸った。続いた紫王は光の刃を生じさせて地面を蹴る。
一気に肉薄したならば一気に斬り裂く。更に蓄積された命中力をも砕けたのを感じる。確かな手応えを得た。
狙撃手達の確実な一手は敵を食い破る大きな力となっている。
「……でも」
大切な花が表情を陰らす姿を、紫王は心配げに見遣る。
敵の弱っている様子が見受けられない。
本当に敵の体力は削れているのだろうか。脳裏に何度そう過っただろう。けれど愛しい花を見たなら目が合って、唇の端に笑みを刷く。ユメは制約を付与する魔法の弾丸を撃ち出した。負けてなどいられない。
「いい加減ちょっとくらい大人しくならないかな!」
煩わしそうに腕で叩き落とす炎駒。だがそこで生じた隙を、御伽は見過ごしたりしなかった。
先程己を庇い消滅した千代菊の想いまで載せて、黒き霊光宿した拳を叩きつける。一瞬たたらを踏んだ炎駒はそれを避けきれない。
「これでどうだッ!」
連打の応酬。鬱陶しいとばかりに身を躱したなら、獣は跳躍する。
「何!?」
反撃は御伽へではない。しなやかな俊敏さで炎駒は駆ける。辿り着いたのは沙季の傍ら。
鋭い牙。
黒い焔が迸る。
倒れた沙季の頭蓋を砕こうと、する。
「危ない!!」
千代が滑り込む。背を壁にして、牙を防いだ。乾いた息が漏れる。
日方が傷を癒すために走る姿を見て、その時ユメは気づいた。仲間が死に至るのを見捨てられるわけがない。しかしそれを防ぐための共通認識は、現状で存在しない。
「……これは、ディフェンダーばっかりに任せておくわけにもいかないか。誰でもいいから、護るのに最適な人が動かなきゃ」
戦いはすべからく状況が錯綜するもの。
万一の仲間の死亡は誰もが防ぎたいと思っていたが、そのためにどう動くかという情報共有に欠けていたと理解したのだ。となれば、がむしゃらにでも庇うしかない。それが手数として無駄が生じるものでも、だ。
逆に言えばそうして守る事が出来得るからか、危機的状況と言い切るまでには至らない。闇の淵へはまだ遠いと感覚で把握する。
わだかまる熱風で、投光器のひとつが吹き飛び転がる。
●肆
命中率を重視した戦術は決して問題のあるものではなかった、いや上策だったと言っていい。表にこそ出さないようだが、確実に相手を追い詰める事に成功していただろう。
しかし強敵相手だからこそ、誰かが狙われた時や誰かが危機に瀕している時。動揺も無駄もなく行動出来るかどうかで、戦局は大きく傾いていく。
戦場とは苛烈なもの。厄介な者や弱い者から倒されるのは当然だし、命を奪われる事も、想定しなければならなかったはずだ。
息の根を止めんとする事で灼滅者側の動揺を誘うほどの知力がある敵ならば、尚更に。何度も執拗に戦闘不能者の首を取ろうとする敵の動きに、ダメージ以上の疲労を蓄積させられるのは事実だった。
膝を地面に落としたのは千代だ。
「……ごめん。もう、厳しいみたい……!」
本当は最後の最後まで皆を護りたかった。
視界が滲む。
いつかは皆死んでいく。けれど、それは今じゃないよね?
「みん、な。……しぬこ、との。ないよう、……に」
千代は意識を手放す。倒れこんだ姿を見遣った御伽は苦さを胸中で持て余す。
既に沙季の他に、盾役として奔走した日方が倒れている。千代菊を除けば千代で三人目だ。人数としてはまだ窮地とは言えぬ状況ではあるが、巧みな列攻撃の塩梅に、一撃で屠るほどの威力のある単体攻撃。癒せぬ傷が蓄積し続ければ、誰一人として余裕のある者などいない。
残る盾役の櫂も肩で大きく息をしている。対して、炎駒もまだ戦意を失わない。表面に数多の傷を負っているにも関わらず、である。
「まだ終われないのに……!」
櫂は更に淡青の帯を展開させ、紫王の傷を癒していく。その間に獣が馳せ、見せつけられた光景に目を剥いた。
千代の首に爪を立てる。それを見せつける時間もさほどないという事は、敵にも余裕はないのだろう。
爪の先には赤。
気持ちが身体に追いつかない。手が届かない。足が動かない。
明確な『死』を目の前にして、脳髄に光が走った。
「お前がどれだけ強かろうと負ける気なんかねぇ」
強敵には敬意と憧憬を抱くのが御伽という男だ。敵から常に放出される風、全身を焼くそれに嬉々としてしまうほどに。
死線の先、その更に先へ。血の滾る感覚に口角を上げる。
そして、呟いた。
「――焼き尽くしてやるよ」
逃げ場などないのだと宣言するかのように、凄まじい勢いで灼熱の幕が展開された。絶望でも犠牲でもなく、生きる為に。
「覚悟なんて、とっくの昔に出来てんだよ」
炎が凝縮される。その炎を殺気に纏わせたなら、短く息を吐いて、刹那。
怒涛の連打が獣に見舞われる。先程と同じ技だが威力はまさに桁違い、幾度も幾度も抉ったならば流石の炎駒も堪らず叫びを上げた。
御伽の気配は既に闇に寄るもの。
その場にいる灼滅者すべてが即座に理解した。
「行こう! まだ出来る事があるよ!」
「そうだね。もう少し粘ったって、悪くはない」
ユメと紫王が息を合わせて走り出す。紫王が高速の動きで脇下から斬り上げたかと思えば、ユメが炎を纏った流し蹴りを食らわせる。
二人を視界に映せば、思い描くは優しい色した愛しき人。
また笑いあう為に。ただいま、と言う為に。
「恐怖を呑んで吼えてやる」
千切られても、燃やされても。
生きてさえいれば勝ちだ。
必ず帰るとの思いを糧に力を籠め、小太郎は聖剣の刃を非物質化させる。狙うは敵の霊魂ただひとつ、御伽が殴りつけた箇所目指して一振り。
「おおおおおおおお!!」
渾身の力で叩き込む。肉を断つ、骨を断つ、魂を断つ。最後の最後まで振り下ろせば、胴の下まで真っ二つ。
咆哮。
洞窟すべてを震わせる。叫びと共に獣は徐々に灰塵となり、霧散していく。
呼吸を整えながら駆け寄り、櫂はその名前を呼ぶ。
「……野乃」
炎が更に燃え盛る背中。お守りの黒の組紐が揺れる。
――倒れてる奴らを連れていけ。
ごく小さな声が、灼滅者達に最後の仕事を言いつける。奥へと歩き出していき、やがてその姿は見えなくなった。
洞窟に静寂が訪れる。
炎の担い手の行方は、闇の向こう側。
| 作者:中川沙智 |
重傷:西羽・沙季(風舞う陽光・d00008) 科戸・日方(暁風・d00353) 鳴神・千代(ブルースピネル・d05646) 死亡:なし 闇堕ち:野乃・御伽(アクロファイア・d15646) |
|
|
種類:
 公開:2016年10月12日
難度:難しい
参加:8人
結果:成功!
|
||
|
得票:格好よかった 8/感動した 0/素敵だった 0/キャラが大事にされていた 0
|
||
|
あなたが購入した「複数ピンナップ(複数バトルピンナップ)」を、このシナリオの挿絵にして貰うよう、担当マスターに申請できます。
|
||
|
シナリオの通常参加者は、掲載されている「自分の顔アイコン」を変更できます。
|
||