
クラブ同窓会~秋色収穫会
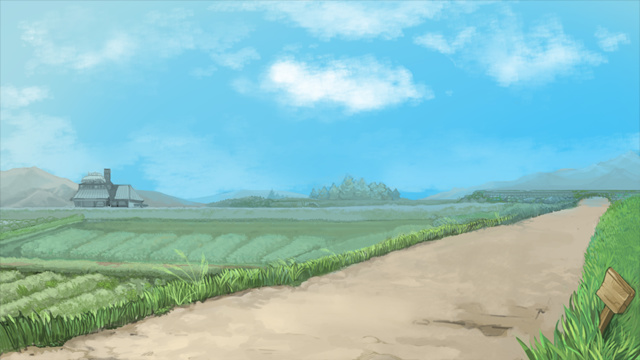

「あら、腰を? 大変ですね」
秋空の透き通る、よく晴れた日の昼下がりの事だった。ある病院の中庭に置かれたベンチで椿森・郁(カメリア・d00466)と一人の患者が話をしていた。
農学部を卒業後、管理栄養士となった郁は病院での栄養指導のほか、資格を活かし食品や栄養素に関するライターとして細々と活動している。左薬指には結婚指輪、結婚後も旧姓で仕事をするのは割とよくあるお話だ。
そうして忙しく日々を過ごす中でも患者さんとの世間話を通し、困りごとがあればそれを解決出来る手段を持った友人の紹介などを行っていた。様々な才能を持つ友人達、困りごともその中の誰かしらが解決出来てしまう訳で評判は上々。必然的に広まる噂話を聞いた患者に呼び止められて、こうしてベンチで話していたところだった。
「そうなんです、おじいちゃん、私が今こんなだから無理しないでって言っておいたのに」
「あはは……それで、人手が欲しい、と」
「ええ、どなたかいらっしゃいますか?」
すみませんこんな事で——そう申し訳なさそうにする患者へと、郁は安心させるように笑いかける。
「知人達に声を掛けてみますよ、勿論、私もお手伝いします」
やがて、患者を見送った郁は暫し空を見上げ思案して、それから携帯を取り出し電話をかける。
「——あ、私だけど、今は大丈夫かな? うん、ありがとう。突然なんだけど、よければ『芋掘り』しない?」
腰を痛めたおじいさんの困りごと、それはかなり広い畑の芋掘りが出来なくなってしまったという事だった。秋の味覚さつまいも、採れるのはほくほくさとねっとり感のバランスが良く万人受けする紅あずま。大したお礼は出来ないけれど、その場で食べる分なら焼き芋にしてもいいと言っていた事は説明の中にしっかり添えて。
「もし宛てがあれば他にも声を掛けて欲しいんだけど、どうかな? 芋掘りに詳しい人とか大歓迎」
久しぶりに集まれたら嬉しいし。そう告げた郁は、よろしく頼むよと添えて電話を終える。そして立ち上がり、身体を伸ばしながら腰に手を添えた。
「……自分の腰は大丈夫だろうか」
呟きはすぐさま無かった事にした。
きっと大丈夫。あの頃も今も、自分達はとてもとてもタフだから。
■リプレイ
●秋色の時間
見上げた空はあの昼下がりと同じ澄んだ青色をしていた。かざした手をそのままに視線を落とすと、今度は一面の緑色。所々に色があせたり、枯れかけたりした葉が見て取れるのは、この一面に広がるさつまいも畑が教えてくれている収穫の合図。
十年という時を経ても友人達が快く集まってくれた事が嬉しい。椿森・郁(カメリア・d00466)は見知った顔に手を振りながら、友人達と同じく手伝いを名乗り出てくれた夫、修太郎へと目を向けた。
軍手にジャージ、長靴装備。やる気に溢れた互いの姿もまた、嬉しい。
「さつまいもについてのプリント?」
郁が手にしていたプリントを一枚貰い、修太郎が目を通す。管理栄養士らしくさつまいもについて簡単に纏められた内容に流石、と声が漏れた。
皆それぞれ、楽しい一日を。
そんな郁の声が聞こえたような気がして静は口元を緩める。他ならぬ郁の頼みだと卒業後も連絡を取り合う友人達に声を掛ければ、馴染みの面々が集まってくれた。
「孤児院の子供達にも芋掘り体験ってさせてみたかったしね」
まずは私が学びに、とジャージ姿に農作業用帽子を添えたアメリアは貰ったプリントを熟読中だ。
「アメリアは形から入るタイプ……? 似合……うよ……?」
「しーくん先輩、呼ぶならおばあちゃんではなくママ先生でひとつ」
大真面目なアメリアの様子に、陽司は自分の服をつい見遣る。記者活動を終えた足でここへ来たものだから、この場では少し浮いた堅めの服装だ。とはいえ。
「クリーニングは玉先輩とか持ってるだろうし大丈夫だろ」
「ESPクリーニング? 何一つ準備してないけど?」
思わず零れた甘えの言葉に、すぐさま背後から返答が。驚き振り返ればイギリスで会った以来の玉がいつの間にか立っていた。
「こんなのは無計画に臨んで汚れちゃったねアハハくらいで済ませれば良いんだよ」
土にまみれたって死にはしない、気にせず競争でも何でも楽しんで笑ってしまえばいい。
「ほら、あんな風に」
ひょい、と玉が示した先に目を向ければ、そこにいたはずの静の姿が消えていた。正確には、オオカミに戻った静が畑の中を進んでいた。匂いで目的の位置を嗅ぎ当てて、汚れなど気にせず前足で土を掘り進む。緑の隙間から覗く尻尾が揺れているのは本能が刺激されているからだろうか。
「尻尾カワイイ」
「やっべえ! 静パイセンだけに格好いい思いはさせませんぜ!」
尊敬する郁の為にもと、服装の心配も忘れて静を追う陽司。そこへ底抜けに明るい声が飛び込んだ。
「とにかく穴を掘ればいいのですわね、うおー。うおー……? お芋はどこですのー、静様ー!」
畑の中からひょこりと顔を出し、静を探す残暑の姿。少し前に『わたくしお嬢様ですから芋掘りとかとっても得意ですわ!』と言っていたような覚えがなくもないけれど——呼び声に静が顔を上げ、残暑を呼び寄せた。
「この下に大物がいるよ」
「え? ここにありますのね! わんわん、わわんわん、ですわん?」
「ここ掘れわんわんじゃないっての。あ、陽司はこっち引っこ抜いといてよ」
「お玉様、お玉様、ここほれにゃんにゃんはありませんの?」
「にゃんにゃんの出勤には燃料のお芋が必要となります」
軽快なやりとりにアメリアは思わず笑う。安全に綺麗に掘れる方法や、大きな芋の探し方を子供達に教えられるよう勉強したいと思っていたけれど、目の前の光景は破天荒な楽しさに溢れていた。
「アメリア様、芋掘りに大事なのはハートですわ!」
「静パイセンやっべえ! この芋でっけえ! 一人じゃ無理! 誰か手伝って! お嬢様! アメリア部長〜!」
大物を掘り当てた残暑が両手でそれを掲げながら泥付きの笑顔で叫ぶ。傍らで陽司が必死に皆を呼ぶ声が響く。確かにそうかも、と頷いて、アメリアは仲間の元へ駆け寄った。
「ふふ、お天気もええし、楽しいねぇ」
「ですね!」
賑やかな畑を見渡して笑みを零す保に噤が大きく頷く。詠も含めた三人の願いでアドバイス指導をしていた郁も嬉しそうだ。
「とまぁ……一般的に言われるコツについてはこのくらいだけど——」
「静さん、元気いっぱい」
「うん、あんな感じでいいと思うんだ」
静オオカミの活躍に詠が目を輝かせているのが分かったから。郁と保が目を合わせ、手で『OK』と示せば詠の「へーんしん!」という掛け声が響いた。
保は噤と、真剣な表情でツルを辿る。真剣ながら噤は尻尾を振り振りと。こうやって身体を動かしての作業は楽しくて、お芋を見つけ、傷つけずに掘り出せた時はもっと嬉しい。山が出来る程に収穫をして一息吐くと、ちょうど詠と静の芋掘り対決が始まったところだった。
「あ、私も参加しちゃう。ふふふ、負けないぞー!」
「勝負たァ聞き捨てなんねえ! 俺も!」
飛び入り参加は誰でもOK、優勝者には、一番大きな焼き芋を。
「この芋のツルさ、観葉植物みたいに育ててるの見た事ある。うちでちょっとやってみていい?」
「芋のツル育てるのか、うんやってみよー」
形の良いものをくるりと回しながら言った修太郎に、郁は興味津々同意した。芋掘りをした覚えは何となくあったけれど、改めて調べてみると新たな発見や興味、小さな頃には気に留めなかった事もあって。
「ちゃんと芋の周りの土を柔らかくして掘らないと、引っ張った芋が途中で割れたりす……」
「……なるほど」
言ったそばから伝わる芋の割れた感覚。静かにそれを拾い上げた郁は修太郎と目を合わせる。
「……これは焼くね!」
小さい頃の自分も、同じように笑っていたのだろうか。
家にあった筈のゴム手袋が無かったのは何故だろう——代わりの軍手をはめながら、小太郎はこれから挑む畑を見渡す。息子に借りたシャベルを右手に、芋の掘り方動画が流れる端末を左手に。けれど見よう見まねではどうもやり辛いし、何かが違うと思えてならなかった。
「んー……」
釈然としない様子で顔を上げた小太郎は、その直後思わず瞬いた。そこにいたのは楽しそうな人々ばかり。
「……あぁ、なるほど」
呟いた小太郎は端末をしまい、代わりに両手でしっかりとスコップを掴んだ。
中学生の時に出会い、今でも時々会う大好きな友達。それが不滅の【ピースフル同盟】だ。
「芋掘り体験して人助けにもなるっていいことづくめ! 任せて、野菜作りは授業でもした! タローもお芋好きだしね!」
「さっすが茉莉ちゃん・ザ・炭水化物ヒーロー!」
畑を真正面に据えて仁王立ちする茉莉と、その隣で尻尾を振る霊犬タローを尚都がすかさず盛り上げる。その様子に顔をほころばせながら、希沙は持参したゴム手袋を藤乃へ見せた。
「ふじは持ってるかな、使う?」
「フフ、藤ちゃんや、あたしの軍手も使うかい? 右手と左手で二刀流っぽくない?」
くるりと振り返った尚都が少しふざけて問うてみれば、藤乃は思案するように口元へと指を添える。
「……なるほど、両手に違う装備であれば収穫率が倍になりそうな」
とても真面目に両手装備を終えた藤乃はスコップを手に畑の中へ。ピンポイントで突き立ててしまいそうな予感を覚えた茉莉は土の上に円を描いて、この辺にいる気がする! と藤乃を呼び寄せた。
「ここですか? ——えい」
迷いなくスコップを突き立てた瞬間、響いたのはザクリという鈍い音だった。スコップを引き抜こうにも抜けずに固まった藤乃はどうにか仲間の顔を見る。
「……焼く前に真っ二つですが食べられますよ、ね」
「大丈夫ふじ! そゆのが美味しいよ! 多分きっと!」
「おいしくいただこう!」
「掘れればよし! あたしも! ほら! とーれた!」
藤乃に続けとばかりに勢い良く立ち上がった尚都が特大のお芋と奇妙な形のお芋を両手に掲げた。けれど沸き上がる拍手に決めポーズをしようとした瞬間、走ったのは腰への激痛で。
「……ごめ、あんま役に立たないかも、あたし」
「な、なおちゃーん!?」
よろよろとうずくまる尚都に皆で慌てて駆け寄った。腰をさすって、おまじないをかけて、無理をしないようにしようと頷き合う。
ピースフルなお楽しみはまだ、残されているのだから。
「あ、掘る時は気をつけてねー」
「はーい!!」
水鳥がのんびりと声を掛けると、元気なふたつの返事があった。わくわく駆け出している長子と長女。水鳥はそれを見守る形で木陰に落ち着いた。
「あ、ちょうど良かった。味見しないか?」
思わぬ声が掛かったのはその時だ。声のした方を向けば、そこには小さな折り畳みテーブルを準備する勇弥の姿があった。
「味見、ですか?」
「焼き芋を食べる時に振る舞おうと思って用意してきたんだ。珈琲、嫌いじゃなければ」
テーブルの上には業務用のポットと紙コップ、小さなカゴにまとめた砂糖とポーションミルク。勿論断る理由はない。
「……あ、美味しい。その、足元の子は?」
「良かった。こいつは今日は道具運び。爪で芋を傷つける可能性があるからな」
先刻からくるくる歩き回る霊犬、加具土。宥めるのが大変だったと笑う勇弥に水鳥も笑う。その中で水鳥が感じるのは、時の流れと人の成長だ。子供の手を引き外に出て、初めて会う人もたくさんいる場にやって来て、こうして自然に人と会話をしている自分は昔だったら想像も出来ない事だった。
あの頃から、今へ。
慌ただしい日常——結婚式の準備から離れ、二人で息抜きもいいかと思いきや。
「結構な重労働……だと……」
畑を見渡し遠い目をする秋帆の服を、隣にいた千穂が引く。
「絶対的に美味しいお芋が待ってるわー」
千穂の言葉はもっともだとスコップを握ればすぐに楽しくなってきた。固い土は自分が、柔らかい所はさりげなく千穂に。
「……ん? 待て千穂これ見てみろ、芋でかい、すげえでかい!」
そうして出会った戦利品を掲げる得意げな顔と、満喫している様子が可愛くて、千穂は笑顔と拍手を贈る。
「さっすが秋帆くん! ほんと、昔から持ってるわよねー」
「三十路過ぎても別に変わらねえよ」
それは、出逢った十五の頃から。けれどそう言った秋帆が何かを考える素振りを見せた。そして手にしていた大きなお芋をおもむろに彼女の両手に乗せる。
「……やっぱ、変わったか」
「え?」
泥だらけの手で汚さないように、顔だけを寄せた不意打ちを。
触れていいなんて、あの頃は思えなかった。千穂がいるのがまるで眩しい硝子ケースの向こう側のようで、なのに今はこんなにも距離が近い。
「これからは——俺のだ、千穂」
「……不意打ち、ずるい」
「はは、そろそろ焼きに行こうぜ」
手を伸ばせばすぐに届く。並んで見上げる空はきらきらと眩しくて、どこまでも続くような高さで。今日も幸せだな、と、二人で笑い合いながら確かめ合った。
「——さすが」
やがて、郁は思わずそう零す。
一ヶ所に集められた今日の収穫は、一目見て分かる大収穫で。同じく見ていた仲間達からも歓声が上がる。
「みんな、本当にありがとう。という訳で」
郁は、両手に抱えていたカゴを皆の方へと向けた。
「次のお楽しみ、満喫しよう」
割れたお芋、面白い形のお芋、皆で集めた達成感。それを味わうという時が待っている。
●ご褒美の時間
畑沿いの農道には、穴を開けた一斗缶がいくつか置かれていた。修太郎が中を伺えば、先に準備をしておいた甲斐もあって熾火となった木炭が見える。
「先に準備しておいて良かった」
やっぱり、早く食べたいから。
いつぶりだったかと思い返せば小学生の自分が脳裏に浮かぶ。あの時は先生が焼いてくれたけれど、今は自分が焼く側だ。
「——大人になったよなー、僕ら」
すぐ近くの小川でさつまいもを洗って、新聞紙で包んだらそれごと再度水につける。更にアルミホイルでしっかり巻いたら、あとは火加減を見ながらじっくりと焼くだけだ。
そして今は、それを始めてから40分程が経過した頃合いだった。
「お疲れさんですえ。噤さんも、詠さんも、はい」
「保先輩ありがとうです。わ、ほくほくです!」
「あちちち……!」
保から手渡された焼き芋を軽く手の中で転がして、ふたつに折ってみれば噤と詠の目が輝く。鮮やかな、ほくほくの黄色が眩しくて、口に含んだそれは思わず笑顔になるほど甘い。
「おじいさんにも、感謝やねぇ」
よほど楽しかったのだろう、水鳥の子供達もまた目を輝かせ、水鳥が冷ましてくれている焼き芋を見つめていた。
「まだ熱いよ、気を付けてね」
わぁいと響く歓声に、勇弥は自分を見上げる加具土を見遣る。自分の分を少しだけ取り分けて、頑張ってくれたご褒美として差し出した。用意した珈琲は大盛況、甘い焼き芋に良く合っている。
頬が緩み、心が満たされる。
「はいタロー、焼き芋だよ!」
茉莉とタローは焼き芋を半分こ、ほっこりうまうまと堪能していた。この頃には尚都もすっかり復活して、久しぶりの美味しさに感激の声を上げている。真っ二つにしてしまったお芋の味はけれど格別で、藤乃も柔らかに笑みを深めた。
「焼きたては、バター落としたら最高やよ!」
片手に自分で収穫したファンキーな形の焼き芋を、片手にバター入りの瓶を持つ希沙には皆揃って目を輝かせる。おすすめバターを多めに乗せて、溶けきる前に食べれば感じたのは高級感と幸福感。
「はー、おいしい。しあわせ」
今も昔も変わらずに、皆ではしゃげる事がこんなにも。茉莉の言葉に藤乃も思う。眩しい笑顔の一時に、尽きぬ感謝を笑顔で返そうと。歳月を重ねても、皆が変変わっても、変わらないものがここにあるから。
「すごい……驚くほど美味しい……」
その頃、景色を堪能しながら食べようとうろついていた小太郎が近くに差し掛かった。今度は家族で——そんな事を考えていると記念撮影用のカメラを準備する希沙の姿を目に留める。
「あれ?」
「……え?」
目が合った瞬間、夫はゴム手袋が見当たらなかった理由を、妻は夫がここ数日何かを熱心に調べていた理由を、理解した。
特に沢山収穫してくれた静達と暫くの会話を楽しんでから、郁は木陰に腰を落ち着ける。皆の様子を眺めていると修太郎がやって来て、同じように隣へ座った。
「珈琲貰ってきた」
「ありがと。じゃあこれ、半分こ」
珈琲を受け取って、半分にした焼き芋を手渡して。あの時と似ているな、と郁は不意に思い出す。
「あの時、修太郎くんも誘って珈琲飲んだっけ」
「……ああ、もうそんな前かあの依頼。まだお互い苗字呼びだったね」
あの頃から、今日まで。十五年前に交わしたゆびきりの約束はずっと続いている。またゆびきりしようか、と笑みを深めた修太郎に郁は頷き小指を差し出した。
「もっと増やしたいな、ふたりで行く場所」
「珈琲を飲みにでも、さつまいも掘りでも、何でも付き合うよ」
だからまた一緒に、手を繋いでどこかへ行こうという約束を。
肌寒いけれどあたたかな秋の一日はまだ続く。
笑い声を響かせ、笑顔を咲かせ、続いてゆく。
| 作者:笠原獏 |
重傷:なし 死亡:なし 闇堕ち:なし |
|
|
種類:
 公開:2018年11月22日
難度:簡単
参加:19人
結果:成功!
|
||
|
得票:格好よかった 0/感動した 0/素敵だった 9/キャラが大事にされていた 0
|
||
|
あなたが購入した「複数ピンナップ(複数バトルピンナップ)」を、このシナリオの挿絵にして貰うよう、担当マスターに申請できます。
|
||
|
シナリオの通常参加者は、掲載されている「自分の顔アイコン」を変更できます。
|
||