
Thanatos


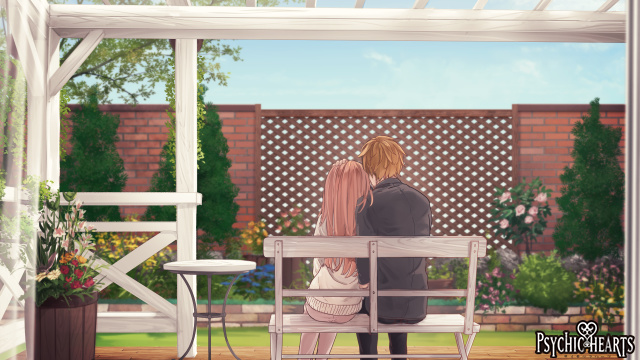

●死に直面したその時
あなたは自身が死に直面したその時、何を思いますか?
過去のこと? 遺していく愛する者のこと? 後悔? 絶望? それとも――安堵?
あなたは近しい人が、大切な人が、愛する人が死の指先に絡め取られそうになった時、何を思いますか?
どんな行動を取りますか?
何を告げますか?
不安、絶望、慟哭、焦燥、感謝――笑顔?
これは実際にあった、あなた、もしくはあなたに近しい人、大切な人、愛する人の命の危機。
これからの未来に訪れるだろう、その時。
または……「もしかしたらあったかもしれない」夢の中の出来事かもしれない。
年齢、状況、関係によってそれは千差万別でしょう。
死が遠のいたときに感ずるものも、同様。
何を思い、何をするか――それには答えなど無いのです。
■リプレイ
●其に触れし時
死に直面した時、どのような想いをいだき、どのような行動を取るか――星の数ほどの選択肢。
●
それは、雷歌が高校へと入学する直前のことだった。出来上がった高校の制服を取りに行った雷歌が帰宅すると、異変が待ち受けていた。
「あつっ……!?」
触れたドアノブは異様な熱さ。まるで燃えているよう――とっさに上着の裾を使い、熱さから手を守りつつドアノブをひねる……だが開かない。
ガシャン! ドゴッ!
「オヤジ!?」
中から聞こえてくる破壊音に、雷歌は室内にいるはずの父を呼ぶ。
「逃げろ!」
だが返ってきた父の声は、切羽詰まったモノ。そしてどこか希いを乗せた色をしていた。
「くそっ……!!」
逃げろと言われて素直に従えるものか。雷歌は扉に体当たりを繰り返し、更には近くにあった消化器で殴りつけた。
扉をぶち破るまで、どれくらいの時間がかかったのかはわからない。
むわり、押し寄せる熱風。目の前に広がるは炎の海。
そして、血まみれで横たわる父と、真っ赤に燃える獣。
雷歌が理解ったのは、唯一つだけ。
「お前、がっ!!」
一瞬で、血が沸騰したようだった。その燃える獣に殴りかかって、体中に走った痛み――圧倒的な『力』を見せつけられたと気づくいとまも与えられず、意識を奪われた。
次に雷歌が目を覚ました時一番に目に入ったのは、真っ白い天井。あの渦巻く赤はまるで夢だったかのように――夢なら良かった。
――お父様は……あなたに覆いかぶさって亡くなっていました。崩れた瓦礫から、あなたを守るように。
人づてに聞いた父の最期。
今でも記憶に残っているのは、最後の最期まで、誰かを護る姿と、言葉。
――生まれてくれて、ありがとう、雷歌。
「あの日救われた命で、今度は俺が誰かを護る」
●
「神童さん、宜しければ、お話聞いて貰えませんか」
采に請われた瀞真は、頷いて。ふたり、和室で向かい合う。
「むかしむかしのお話ですわ」
緑茶の入った温かい湯のみに触れながら、采は口を開く。
それは学園に来る前の話。采は長い間昏睡状態だった。その間の『記憶』を采は語る。ソウルボードに居座るシャドウと、ずぅっと盤上でゲームをしていたのだと。
「ひとつ勝てたら、ひとつ身体のどこかを治して貰えます。
ひとつ負けたら、ひとつ身体のどこかが壊れまして。
そないな、ゲームですわ」
そのゲームは繰り返し、繰り返し行われた。いつ終わるともつかぬ盤上遊戯。
「目覚める直前まで、ちょうど、せん、と、ななつ、め。なんぼ勝ってもなんぼ負けても、これ、いつまで続くんやろなぁ、思てて」
訥々と語る采の横に、ふと、霊犬が姿を現した。寄り添うように、彼の手の届くところに座る白い犬。
「次負けたら、しまいやなぁ、という時に、うちの子が現れたんです」
そっと、采はその白い毛並みを撫でる。向ける瞳も長い指先も、優しく、優しく。
「それが死に直面した最初やね」
「僕が聞いてしまってよかったのかい?」
指先を温めるかのように湯のみを包み込む瀞真の問い。
「なんでやろ、なんだか、神童さんには話せました、わ。おおきになぁ」
指先に感じるぬくもりは、あの頃と変わりなく。
はんなりとした笑みを、采は浮かべた。
●
冬の埠頭――その風ですら冷たいというのに、底知れぬ昏き水の中はいかほどだろうか。
躊躇いが、恐怖が無かったわけではない。理不尽に感じなかったわけではない。けれども。
ザッ……僅かな浮遊感からの衝撃と、体を包み込む刺すような冷気。海の中は暗くて、冷たくて、苦しくて。
でも、ゆまは少しホッとしていた。
(「もうこれで誰にも迷惑をかけなくて済む。わたしを引き取ったせいで、親戚中と大喧嘩をしたおじさん。わたしの事を心配し続けてた、りっちゃん」)
浮かぶのは他人のことばかり。他人の心配ばかり。
(「他にも友達や先生や」)
これで、もう迷惑をかけなくて、すむ――その思いばかりが、否、その思いだけがゆまの心を満たしていた。
(「くそっ……!」)
心の中で悪態をついたのは、彼女を連れ出した相手に対してか、それとももっと早く動け、と自身の足に対してか。
律は走っていた。
彼女が、学校でいじめられている奴らと埠頭へ行ったと聞いたから。
「!!」
埠頭まであと少し――律のいる方向へと、まるで逃げるように向かってくる集団には見覚えがあった。だが、声を掛ける前に漏れ聞こえた言葉が、律の目の前を漂白したのだ。
「あいつ、ほんとに飛び込んだ!」
集団はその後、責任の所在を探り合うような言葉をかわしていたが、律の耳には届いていない。
(「――アイツは泳げない」)
足を止めず、なお加速して。一瞬の迷いもなく、冷たい海へとその体を投げ込んだ。
(「絶対に死なせない」)
その想いだけで、昏い水を掻く。
肌を刺すような水の冷たさは、気がつけば感じなくなっていた。むしろ、暖かく包み込んでくれているように感じて、苦しさすら感じなくて。ゆらりゆらりと水の揺り籠に揺られる感覚。
ああ、このまま眠りに――優しく迫る『それ』を拒まぬゆま。
だが。
ぐっ……何かに強く掴まれた感覚。思わず呼んだ。
「りっちゃん?」
「!!」
心臓を鷲掴みにされた感覚。目を開けた律は、無意識に服の左胸部分を掴んだまま、彼女を探した。
彼女はすぐに見つかった。隣で居眠りをしていた彼女は、あの時より6年の時を重ねていて。今、律が沈んでいた世界は、夢だということがしれた。
あの時、昏い海の中で彼女を見つけられたのは、奇跡だったと思う――目の前にいるゆまが、本物の彼女であるのか確かめるように、思わず手を掴んだ。
すると、震えた睫毛、開いた瞼。瞳が律を捉えて。
「りっちゃん?」
自分の手を掴む彼の瞳が、とても心配に揺れているように見えたから。
(「ごめんね、いつもそんな顔させて」)
複雑な想いをすべてこめて出た言葉は。
「ありがと」
切ない微笑みと共に告げられた言葉に、たくさんの思いが込められていることに律は気づいていた――全てではないけれど。
「バーカ」
一言、返してそっと胸をなでおろす。
だが、このときの律はまだ知らない。
15年も経たずに、彼女が本当にいなくなることを。
●
白い、白い、函の中。
いくら見舞い品で埋めても隠せないのは、特有の消毒薬の香りと死の影。
12に満たぬ少女が抱くのは、幼き日に与えられた、ピンク色したウサギの綿人形。
泣いて泣いて泣いて、咽も嗄れて。
何度も同じ言葉で諭されても気持ちの置きどころはない。
楽になるんだ――ならばどうしてこのまま楽になれないの?
父横たわる寝台に縋り、少女は啼く。
わたしがわるいこだからあなたを救えない、と。
ごめんなさい、いやだ、と。
早く、助けられる力がほしかった――どうしてわたしはわたしなの、と。
命がその手をすり抜けて、遠いところへ行ってしまう。
伸ばした手が、もう届かないのがわかる――こわい。
間に合わない、間に合わない、間に合わない。
どうして大人たちは諦めた顔をしているの?
どうしてわたしは身代わりにすらなれないの?
もっと満点もとるし、欲しいものも我慢する。
なんだってする……だからゆるして。
祈るのは――。
「……パパ、かみさま、おねがい」
祈る相手はそれしか知らなかった。
「――夢すら今までは、見られませんでした」
生きててほしかった――その想いは当時のニゲラも今のニゲラも変わらない。
今になって現れた泡沫の夢。其れは何を意味するのか。
死に目に間に合わなかった彼女を責めるためか、赦すためか。
そもそも夢にすら見ることができなかった、それは彼女の自罰心ゆえではなかろうか。
だとすればこれは、赦しなのかもしれない。
●
「!?」
身体に走った強い痛み。これが双子特有の感覚共有だと気がついたのは、だいぶ前だ。
南守はその痛みと直感に従って、風花舞い散る路地を行く。
導かれるようにたどり着いたそこは、公園。やや降り積もった雪に常では現れぬ『跡』を見つけて――。
ましろい雪に咲く赤い華は、鉄の香りを漂わせる。
(「此れで僕は自由だ。あの人の……菊乃さんの元に逝ける……」)
己が斃した仇の咲かせた華に一片の意識を割くこともなく――否、その余裕さえないのだ。
久里は、何とか動く右手で鋼糸を繰り、己の首に巻き付ける。仇敵の命を余さず削り取った彼には、もはやほとんど力は残されていなかった。
「!?」
本懐を遂げた久里が、あと少し力を振り絞るだけ――その時腕に感じたのは、強い力。
樹にもたれ掛かったその姿は、よく知る人のもの。その首に巻き付いているのは――。
南守は反射的に地を蹴った。彼との距離を詰めて慌てて掴んだ右手には、驚くほど力が残っていなかった。
それでも。
「お前、何やってんだ!」
意図は知れたから、口から出るのは、怒り。
「何です……邪魔をしないで頂けますか」
目の前にある自分と同じ顔に、久里の心に苛立ちが浮かぶ。
「……死ぬつもりか?」
「煩い」
「そんなの邪魔しない訳に行くかよ!」
南守にはその選択を邪魔しない理由がない。
「お前は俺が求めてやまなかった、ただ一人の血の繋がった家族なんだ。死なせない、死なないでくれ、頼むから……!」
懇願するような南守の言葉は、久里の心には響かない。ただただ、煩わしい。
「僕の気持ちも知らず、自分勝手な。僕がどんな思いで生きてきたかも知らない癖に」
「気が合う訳じゃない、ムカつくことも多い。それでも俺にとって唯一の存在なんだ……」
ああ、煩い――久里の心を占めるのは、ひとつの感情とひとつの希望。
(「ねェ菊乃さん。僕も今そこに……」)
煩わしいものはすべて切り捨ててしまおう――残された力を振り絞って、久里は鋼糸を引く。南守の手ごと落としてもいい、希いが叶うなら――。
「!?」
「!!」
鈍い音、同時に手応えのなくなった糸。
鈍い音、同時に痛みに咲く華。
「……菊乃……さん……?」
呆然として紡いだ名前。聞こえてくるのは懐かしい声。
――『人』で、居てね。
千切れ、緩んだのは糸だけではない。限界を超えていた久里の意識もまた、同じ。
「ほら……死なせないってよ」
ほっとした表情をしているだろうことは、声色だけでわかった。自身で支えることすらままならなくなった身体を、南守に支えられたのがわかる。けれども、顔を、瞼を上げる力がもうない。
(「あァこんな筈じゃ……無い…のに」)
不本意なはずなのに、受け止められたもうひとつの身体から聞こえる同じ鼓動に、心地よさを感じそうになる。
まるでもともとひとつであったことの証左のように、混ざりあった血が、雪に赤い華を咲かせた――。
●
あれから一年後――わんこは世界中をぶらぶらと放浪していた。
あらためて巡ってみれば、世界には自分の知らないこと、知らないものがたくさんで。
その土地固有の文化や風習に刺激を受けたりもした。
人々がエスパーとなりゆく未来、世界が変わってゆくことで、それらも自然に変化してゆくかもしれない。だから今、こうして自分の目で見て識るのがとても重要で、有意義な時間だと感じていた。
けれども、そんな日々は永遠にはならなかった。
その時わんこが滞在していたのは、ヨーロッパの片田舎。年老いてからようやく授かった子どもだと、3歳の男児に愛を注ぐ夫婦の家に泊めてもらい、手伝いをしながら過ごしていた。
「わんこ! ダニーを見なかった!?」
血相変えた母親の様子で状況を察したわんこは、すぐに走り出た。ダニーは好奇心旺盛な3才児。幼子は時に大人が驚くほどの速さで駆けていく――だが、灼滅者なら追いつくのは容易い。
「ダニーちゃん、止まって!」
わんこはすぐにダニーを見つけた。だが、彼は、目の前の、自分から逃げゆく猫しか見えていない――その先は、車道だというのに。
予想に違わず車道に飛び出した彼。その真ん中で躓いて転び、火のついたように泣き出した。息を呑んだのは、わんこと、車道を走ってきたトラックの運転手。
「っ……!!」
車道を挟んだ向かいは、幸いにもほぐされた牧草が積み上げられている。ならば――わんこは躊躇わずに車道に飛び出し、片手でダニーを掴み、そして投げた。
甲高いブレーキ音、幼子の無き声、目撃者の悲鳴、全身を打つ鈍い痛み――灼滅者ならばトラックに轢かれてもどうってことないから、大丈夫――思わず閉じた瞳を開けたらそう伝えよう、わんこは思った。
「えっ……」
「確かにぶつかったよな?」
「ああ、この跡を見てくれよ!!」
トラックに衝突の痕跡は残っている。けれど。
「じゃあ、あの子はどこに行ってしまったんだい!?」
わんこの姿は、どこを探しても見つからなかった。
瞼が異様に重い。
おかしい、このくらいで灼滅者である自分が怪我をすることはありえない。
だから。
「……え?」
瞼を開けたその時は、まだわからなかった。
力を振り絞って上半身を持ち上げて――視界に入ったのは、明らかに知らない景色。
ヨーロッパでも、ましてやわんこのよく知る日本でもない。
「ここは、どこですか……?」
その後、灼滅者・野良わんこの消息は、途絶えたままである――。
●
時は10年後。シエナは魂の分離の実験中だった。
それは、事故。不幸な、とは断定できぬが事故であったのだ。
デモノイドヒューマンである彼女の中の寄生体が、事故により暴走を始めた。『ヴィオロンテ』――赤薔薇の蔦が寄り集まった、深緑色の蔦の集合体――へと過剰なまでに侵食してしまったのである。
シエナの寄生体とヴィオロンテの侵食融合、ついにはそれに引きずられるように、シエナ自身の身体も植物化を始めてしまった。
助けを求める事は、できなかった。
研究自体がダークネス復活に繋がりかねないものだったがゆえに、秘匿を徹底していたからだ。
それが災いとなった。
助けを求める術を見つけることは、完全に不可能だったわけではない。
研究内容を知られるリスクさえ容認すれば――だが、彼女はそれを良しとしなかった。研究内容が知られてしまえば、たとえ命が助かったとしても、彼女は希求することを禁止されるだろう。それは、死に等しい。
ゆえに彼女が選んだ最後の抵抗は、植物化する自身の記録を残すこと、だった。
『お日様が心地良過ぎる』
記録を始めてから、どれほどの時間が経っただろうか。今までの記録を数えればわかるかもしれない。けれども彼女はそれをしなかった。そんな事、どうでも良かった。否、考えもつかなかったのかもしれない。植物化が進むと共に意識が朦朧とすることが増え、記録も徐々に単純化していたからだ。
けれども彼女が、徐々に植物化してゆく現状を受け入れ、楽しんでいたことは、残された記録からわかる。淡々とした単純な言葉のみの記録だが、苦しみや悲壮さを感じさせる単語はどこにも見当たらなかったから。
其れは彼女が完全に植物化し、意識を消失させる直前の記録だろう。
『おやすみなさい』
憎らしいほど礼儀正しく、彼女は眠りについたのだ。
●
2028年12月13日。
「夢を、見ました」
まるで誰かに語るように、望は言葉を紡ぐ。
「真っ暗な世界で私は動くことも出来なくて」
聞き手の様子は窺えぬけれど、言葉は溢れる。
「誰かの色々な感情が、願望が、私を包み込んでくるみたいで、何故か私は穏やかな気持ちでそれらを受け入れたいと思いました」
今、望のいる『そこ』は、真っ暗な、あるいは真っ白な、もしくは真っ青な――不思議な空間。
「どうしてこうなったかはわからないけれど、もういいかな、なんて思ってしまって」
訥々と語る望自身ですら、『ここ』がどこなのかはわからなかった。
「このまま死んでしまったとしても」
自らに迫るそれは、誠に『死』だったのだろうか。かつてそれを視る事ができた望が、それに嫌悪や恐怖を感じなかったのは、ある意味当然なのだろうか?
「そこで私の意識はゆっくりと途絶えていきました」
それが正しく『死』だったとしても、望はその要因を理解していない。理解することができなかった。理解したいとも思わなかった。識る必要性を感じなかったのだ。
学生の頃の容貌そのままの『彼女』は、穏やかに微笑んだ。
「夢を、見ました」
小さな、小さな、銀髪の少女が目覚めたのは、深い深い森の中。自らの視界を塞ぐ目隠しに、そっと触れて。
「……あの夢は、何だったのでしょうか」
呟きは、深い森に溶けて消えた――。
●
2028年――いつもの、夢を見た。
それは学園に入学する前のこと、沙月はまだ15だった。
とある理由で一族から放逐された彼女は、放逐先で恋をしていた。
世話係の少年との間に芽生えた想いは、甘く。ささやかなことで心を満たすほどで。
けれども御神体として生かされていた沙月にあてがわれた彼は、新しい御神体を生み出すための番であることは容易に想像できたから、その運命から逃れるために、必死にもがいた。
だが彼女がその運命から逃れるより早く、運命は破壊されたのだ。
一人の羅刹の、気まぐれによって。
すべてが破壊され行く中、彼は、沙月を護るために羅刹となって力を振るう。羅刹が、彼女まで破壊してしまわないよう――それは世話係としての義務感からでも、番としての使命感からでもなく。
飽いた羅刹が去ったあとに広がるのは、惨憺たる光景。
「っ……!」
明らかに虫の息である彼のそばに膝を付き、沙月は必死に彼の傷を癒そうとした。だが。
「……殺してくれ」
「……えっ……?」
「……もうひとりの私が、……君を殺してしまう前に……」
それは彼の切なる願い。最期の願い。そして、沙月への愛の証明。
本意ではなくとも、自らの手で愛する者の命を奪いたくないから――。
けれども。
だけれども、沙月はその願いを叶えることはできなかった。
愛する者を失いたくない気持ちと、その手にかけたくない気持ちが躊躇わせたのか、それとも他になにか思うところがあったのか、今となっては、もう……。
「……!」
呼ばれ、その声の主を確かめるより早く、駆けつけた妹が、すべてを終わらせてしまったから――。
「っ……!!」
いつも、そこで目が覚める。胸を占めるのは、後悔、申し訳なさ、そして……。
きっと、一生忘れることはないだろう。
(「それでも、全てを抱えて生きていきましょう」)
●
そこは死の満ちる空間。生と死の間で力がぶつかり合い、生が消え、死が増えてゆく。
「……ここ数年……狂えたらどれだけ楽だったか……ねぇ、ボクをもう……終わらせてよ」
神影は、血に塗れたまま敵対者へと語りかける。だがその腕は、その武器は、まるで彼女の意思を無視するがごとく、次々と敵を屠ってゆく。
「終わりたいのに……死にたいのに……それを許してくれない……」
そんな彼女を敵は、どう思ったのだろう。
哀れみ? 嘲り? 恐怖? 憐憫?
だが、まるで意思があるかのように勝手に動く武器が、それを確かめることを許さず敵を沈めてしまう。
いつになれば、いつまで待てば、いつ、いつ、いつ――。
気がつけば身体が、地に落ちていた。
地につけた頬を濡らすのは、地を塗り替えた血の海。
「やっと……楽になれる……お父様……お母さま……兄さま……」
本能的に感じるのは『死』。だがそれは、神風を恐怖で揺らすことはない。むしろそのまま飲み込まれるべく、余計なことはしてくれるなと武器に願う。
そして。
痛みよりも強く感じるのは、安堵。狭まる視界に解放を実感して。
「やっと……やっと……みんな……いまいく……よ……」
最後まで言葉にできたかはわからない。
暗闇の中、もう何も見えず、聞こえず、感じなかったから――。
●
「殺(コワ)しに来たの?」
血にまみれた姿を、意に介さずにハレルヤは笑む。目の前の男は首を振り、告げる。反逆者を見つけ、人の元へ戻るよう、依頼を受けた、と。
「キミ、六六六人衆でしょ。ヒトに従うの?」
やや虚ろな瞳で男を見据えて。
「生きる手段選ばずと言えば、イイなあ」
それは本心か。
「キミみたいになれたら」
「なれる」
ハレルヤの返答に、差し出された男の手。
「居場所はここだよ、ハレルヤ・シオン」
「……」
一瞬、思考が停止した。
蘇る、記憶の糸。
闇落ち時、護衛としてそばにいた、それが――。
「キミで良かった。ヒトは殺してくれないもの」
六六六人衆を頼る事、果してそれは誰の計らいか。
伸ばした手を取らず、ハレルヤは彼との距離を詰める。
斬り合いの再開、その時彼女が手を抜いたのか、それは本人たちにしかわからない。
四肢千切られて、血の海に転がる。『死』を感じるそれは、『ヒト』としてのものか。
絶望に恍惚浮かべ、彼女は願う。
――助けて。
男は迷わなかった。
男の刃が強化硝子を貫き、ハレルヤだったモノは終りを迎えた。
嬉しい、今度こそ、やっと――。
●
203X年、中東の紛争地域の難民キャンプにて。
「難民の避難が先だ、任せたぞ!」
そう告げ、敵勢力に向かう背中。それが確認された最後の姿だった。
「か、はっ……俺としたことが、しくじったな……」
破損したヘルメットはもう用をなさない。脱ぎ捨てたところで四肢から力が抜け、彼は倒れ込んだ。
「この負傷……俺も、ここまでか……だが……」
自分の身体は自分が一番良く知っている。負傷の度合いもしかり。
「難民の、人々は……守ったぞ……」
敵勢力のリーダーは灼滅した。再び攻めてくることはないだろう。部下たちは皆、優秀だ。難民達を無事に避難させ、護っていることは疑いの余地がない。
けれど。
和守は無傷というわけにはいかなかった。
「最期まで、力無き人々の、為……戦ったんだ……悔い……は……な、い……」
それでも彼の心は晴れ晴れとしていた。
常に最前線で戦い、たくさんの人を護ることができたのだから――。
陸上自衛隊三等陸佐 平・和守。
中東の紛争地域、難民キャンプにて部隊を率いてPKO活動中、ダークネスを含む反社会的勢力の襲撃を受け交戦。
部下達に難民の避難と護衛を任せ、自身は殿として残り、敵リーダーの灼滅に成功するが、消息不明となる。
遺体は確認できていないが、現場には血に濡れた彼の装備品が酷く破損した状態で残されており、公式には殉職したものとされている――。
●
少年だった夏の日、才葉の運命を変えたその場所は、誰も知らない彼の故郷。
山奥の廃村――人の住めない故郷は朽ち果てて見る影もない。だが、祖母のいたであろう家屋に彼は居た。
祖母の死を期に堕ちて、自らの手で壊滅に追いやった故郷。
その後、学園で人と温もりを知り、32年目の夏。
ここにあって思い出すのは、祖母と過ごした日々。つらくて悲しくも幸福だったあの頃。
次いで人として歩み始めた学園生活。彼にとって特別で大切な空の青は、たくさんの絆を繋いでくれた。
かけがえのない友を得た瞬間、すべてが克明に思い出される。
大切に、大切にひとつひとつ思い出を紐解いて。
「ありがとう、って伝え損ねちゃったな」
たくさんの楽しかった思い出には、いつも大切な人たちがいた。感謝しても、し足りない。
「行こう」
傍らに立つ漆黒の狼、逢神に告げる。祖母の元へ導いて、とでもいうように。
そっと横たわる。
けれどもいま一度、と閉じた瞳を開ければ、視界いっぱいに広がるのは――。
「やっぱり、空はキレイだ」
瞳に映る空は、あの日見た夏の青と同じ――。
●
あれから30年が経った。
「ねぇ、宗田。……生まれ変わりって、あるのかな」
振り返らずも近づいてきた彼の気配を察し、澪は問いかける。
「……さぁな。考えた事も無ェ」
テラスで腰を掛けている澪に近づいて、宗田はいつもと同じ口調で答えた。
澪は元々人より病弱で、心臓を患っていた。一度は手術で回復したけれど、アイドルとして働いていたことが奇跡なくらい。
余命宣告を受けたのは2年前。以前とは違う、だけど同じ心臓の病だ。
「僕ね。本当に幸せだったよ」
(「残される方が辛いから、僕が長生きするとか言ってたくせに」)
心中で呟きながらも、宗田は澪の言葉を遮らない。
「少なくとも宗田と出会ってからは……幸せだった」
(「だからこそ伝えていた。俺は覚悟のうえでお前を選んだ、だから後悔するなと」)
――澪は呆れるほど、優しいから。
宗田はそっと、澪の力の抜けた手を取る。互いに感じるのは、昔と同じ体温。
隣に腰を下ろし、澪の肩を抱き寄せて、自身に凭れかからせる。
(「どうしよう、離れたくない……目頭が熱い」)
それでも、彼の前ではいつも笑顔でいたいから――その強がりも全て理解した上での宗田の行動、それが澪の涙腺を更に刺激する。
「ずっと隣にいる」
「えっ……?」
「例え別人になっても、魂だけになっても。俺は必ずお前を見つけるし……護ってやるよ。今まで通りな」
「……ふふ。じゃあ、約束ね。待ってるから……」
優しく髪を撫でる手も、ずっと変わらず言葉よりも雄弁で。触れた部分から、彼の心が伝わってくる。
「疲れただろ。いいからもう寝ろ」
いつも通りに、最期まで安らかであるように。それだけを、澪のことだけを願って。
「……、……」
そっと閉じた瞼が、妙に重くて。死期を悟るってこういう感じなのかな――目尻に溜まった涙が頬を伝うけれど、不思議ともう、寂しくはない。
「うん……ごめんね。ありがとう……それから――」
おやすみなさい、世界で一番愛した人。
いつかもう一度、出会える日まで。
それは、悔しいくらいに穏やかな朝だった――。
●
それは、2040年より後のこと――。
「ほら、喧嘩をしたらどっちも謝る!」
児童養護施設で、いつもどおり子どもたちの世話をしていた。
喧嘩した子どもたちを仲直りさせるなんて日常茶飯事で、きっと明日もまた同じこと言うんだろうなぁなんて漠然と感じていた。
けれど。
――パリン。
小さなその音は、雄哉の胸の奥から聞こえた。
音を認識した時には、すでに意識が遠のき始めていた。目の前にいる子どもの顔すらひどくぼやけて見えて、足元もおぼつかない。
そのまま倒れ込んだ時、あの音が何かが割れる音だと気がついた。
(「……ああ……胸に埋め込まれている霊子強化ガラスが……割れて、消えたのか」)
慌てる職員たちの声、自分を呼んでいると思しき声、子どもたちの心配の声も、どんどん遠くなり、判別できなくなり……聞こえなくなっていく。
(「……とうとう、両親と兄の元に逝く日が来たのか」)
誰よりも覚悟はしていたつもりだったけれど。それでも。
(「……愛莉、ごめん、先に逝くよ……」)
浮かぶ気持ちに謝罪と後悔がないとはいえない。
(「でもね、愛莉と一緒になってからの僕は、すごく幸せだった」)
できることならこの思いを、伝えてほしい。
(「ありがとう」)
この、一言だけでもいいから――。
「……、……」
青天の霹靂という言葉は、このようなときに使うのだろうか。
突然の電話は、店が定休日故に自宅に居た愛莉の心を引きつらせた。
――雄哉さんが倒れて、病院に搬送されました。
けれどもその時点ではまだ、頭のどこかに冷静な部分があった。タクシーの中で、親友の朔夜に連絡のメールを送るくらいには。
連絡を受けてすぐに病院に駆けつけた――けれども、愛莉が案内されたのは、病室ではなく霊安室だった。
――搬送された時には、もう手遅れでした。
どこか遠くで、その言葉が響いていた。
雄哉さんにもしもの事があれば、必ず駆けつけるって約束してた。
「……!」
愛莉からのメールを確認した朔夜は、勤め先の病院からすぐに駆けつけた。医師であるからして、メールの文面で何が起きたか、これから何を見るか、予め理解していたはずだった。
「……朔夜くん、来てくれて、ありがとう」
案内された霊安室。朔夜を出迎えた愛莉は、いつものように穏やかに見える、けれど。
「雄哉、すごく穏やかな顔、しているわ。眠っている、みたい」
彼の穏やかな顔は、伝えきれなかった最期の言葉の代わり。
「『霊子強化ガラスが破損した』のが原因、ですって」
穏やかに語る愛莉が、彼女が雄哉に向ける視線が、言葉にする以上のものを表していて。朔夜は涙を拭い、眠る彼へと近づいた。彼の顔は愛莉の言う通り、ひどく穏やかだ。
「いつかはあるって覚悟していた。でも、それでも……あまりに唐突で、夢を見ているみたい」
彼女が泣かない代わりなのか、朔夜の瞳に浮かびそうになる涙。それをぐっとこらえる。
「今までご苦労さま……雄哉さん。君の生き様は僕が確かに見届けたよ。ゆっくり休んでね」
雄哉が穏やかな顔をしているのだから、涙で曇る前にその顔を視界に焼き付けたい――彼の顔を見ながら、朔夜は語りかける。
「僕にかけがえのない思い出をありがとう。後のことは任せて」
「雄哉……ありがとう」
冷たくなった夫の手を握り、愛莉は語りかける。
「もう、無理しなくていいから……」
それは、最期の儀式か、もしくは零れそうな涙を隠すためか。
「ゆっくり休んで……」
雄哉の顔に覆いかぶさるようにして紡いだ言葉。
愛莉の表情は、朔夜からは見えなかった――。
●
2066年12月31日――日本近海の地図にない無人島に、ふたりの男は居た。
学生時代に『殺してやる』と誓ってから早数十年。日付は錠の69歳の誕生日。
「あれから五十年か。お互いすっかりジジイだな」
手にした刀と同じように、眼前の男もこの約束だけは裏切らない――それは葉自身が一番良く知っていた。
「本当はもっと早く叶えてやりたかったが、俺みてェなポンコツに依頼したばっかりに、随分待たせちまった」
ナイフを手に、告げる錠にも、日本刀を手に向かい合う葉にも、歳を重ねた印が容貌に現れていた。それでも衰えぬのは、その技。
(「ずっと、ずっと温めてきた最期だ。ケーキの代わりに鮮烈な痛みを、クラッカーの代わりに血飛沫を。俺の命にリボンを掛けて、人生最期の誕生日を祝ってやろう」)
「安心しろ、お前をひとりにしねぇよ」
互いに詰めた距離、葉の日本刀が錠の喉を貫く。しかし同時に錠のナイフが、心臓にマーキングでもするように、葉に突き刺さっている。
(「これは――18の誕生日にお前が贈ってくれたものだった」)
錠の口からは、ヒュ、と間抜けな空気音ばかりが漏れる。刃が喉笛を貫通しているせいだ。血の泡を唇から噴きながら、目の前の相棒を睨めつける――これでもいつものようにお前を呼んでるつもりなんだ。
波打ち際に倒れ伏したのは、どちらの身体が傾いだのがきっかけか。そんなこと、もはや些末なこと。
痛みはとうにない。あるのは相手への殺意と感謝と、遺していく者達への身勝手な願いだけ。
波の音に重なって、錠の歪な呼吸が聞こえる。
波打ち際の飛沫に、血潮が交ざる。
――懐かしいフラミンゴピンクだ。奈落の底でも逃がしゃしねェぞ、葉。
――しょうがねぇ奴だな、お前も。ほんとしょうがねぇ奴だよ。
波の音を子守唄に、躯は海に。死ぬなら海の傍で。
――ありがとう、相棒――最高の殺し合いだった。
――愛してる。
●
2078年頃、スウェーデン。
寿命による死が近い時、この国では不自然な延命治療は行わない。故に今、ヴェルグは、自然に衰弱の末に死の淵にあった。
思い返すことは多々。
奪った命に思いを馳せることはあっても、後悔はない。
家族、親族も立派にやっている。幸は願えど、心配は皆無だ。
けれどひとつだけ、気になるのは――長い付き合いの友の消息。
連絡を取り合い、時折会いもした。
だが、秘境を旅する彼とのやり取りはスムーズとはいいがたく、長らく連絡が取れなかったり、届く知らせに時差が生じることも多くあった。
(「前回会った時、恐らくこれが最後であろうことは話したな」)
自身の死後に彼が訪れた時、墓の場所を教えるように家族には伝えてある。
死の淵にいる自分にできることは、もうなにもないと分かっているけれど。
(「願わくば――……」)
彼に平穏を。
命が尽きるまで、ヴェルグは祈り続けた。
●
風の暖かさが緑の匂いと花の匂いを孕んでいる。日差しも柔らかな温もりを地に注ぐ――春、だ。
自宅の縁側に腰を下ろせば、心地の良い陽気のせいか、心もふんわりと温まり、滲み出るのは遠き日の思い出。
今まで思い出したことがなかったわけではない。けれども今の木乃葉にとっては遥か昔のことのように思えて、思い出しにくくなっていた部分もある。それが何故か、今日はすらすらと思い出せるから不思議だ。
学園で過ごした青春時代、たくさんの苦楽を共にした仲間たち。最近では朧げになっていたその顔も、今ならはっきりと思い出せる。
法学部を卒業したのち花火会社に就職して。血の繋がりのない自分を愛してくれた家族たちに囲まれて、地主業を継ぐことができた。
最愛の妻、子や孫など家族に、そして友人にも恵まれた人生だったと、胸を張って言える。
家業も人狼としての使命も、やりきった――達成感と満足感。
武蔵坂学園や知り合いの孤児院に寄付をして恩も返せた。
(「思い返せば」)
自分の人生、悔いなく楽しんだものだ――自然と微笑が浮かぶ。
(「ああ、暖かい」)
身体を覆う空気も、胸の中も暖かくて。安堵からか歳のせいか、眠気に足を引かれる。
うとうと……うとうと……。
これまでもこうして縁側でうたた寝してしまうことはあった。いつも誰かが冷えぬようにひざ掛けを用意してくれたり、起こしてくれた。
それまでの間、夢を見る――。
(「ああ、でも……」)
今日の夢は少し違う――違和感と予感。
先に旅立った家族や友人が、まるで自分を待っているかのように、優しくこちらを見ていた。
「今、行きます!」
夢の中で彼らに告げた自分の声は、かつての若々しいもの。姿もそうなっていることに、疑問は抱かない。
走って、走って、走って――息も切らさず、笑顔で彼らの元へ。
春の日差しに包まれて、木乃葉は目覚めることのない眠りについた。
幸せそうな笑顔を浮かべたまま――2091年5月8日。享年88歳。
●
そこはサーカス小屋の天蓋付きベッドの上。いつも、いつまでも変わらぬその世界に、いつもと同じように、手を繋いでふたり、横になる。
ベッド上だけでなく、部屋の中に。ふたりを見守るように囲むのは、子ども代わりの人形やぬいぐるみたち。
普段と変わらない、いつもどおりの添い寝。
普段と変わらない夜、いつもと同じ時間。でも、今日だけは何か違う気がして――エステルはそっと、繋いだ手を強く握りしめた。
怖くないわ――答える代わりに雛は、その手を強く握り返して。
(「愛するエステルがすぐそばにいるもの」)
ふと、思い出したかのように言葉を紡ぐ。
「ねぇ、エステル。ふたりで過ごした日々は、楽しかった……?」
フェイクスイーツが揺らめくカーテンの向こう。地下深くの小さな『世界』。
「子どもも孫もいないけど、寂しくなんてなかったわ。あなたがいつもそばで、支えてくれたから」
あらためて言葉として織り上げるのは、やはり予感がするからか。
「ひなちゃんはいっしょにいてどうだったです? いろいろあったけど、いっぱい幸せにできたよね……」
「ヒナは幸せよ、あなたと出会えて」
身体の向きをゆっくりと変えて、ふたり向き合えば、互いの瞳に宿るものは誓ったあの頃と変わらない。
「むきゅ、いままでも雛ちゃんとずっといっしょにいたもんね……ずっと、いっしょにいたいの……」
「そうね、これからも、一緒に……」
雛のその言葉に安心したのか、エステルは再び背をシーツの海に預けて。
「むにゅ……ねむくなって……きちゃったの……また……あした……なの……」
「エステル?」
瞳を閉じた彼女の名を呼ぶ。応え(いらえ)はいらない。
「……ふふ、先に眠っちゃったのね。ボンニュイ、エステル」
告げて雛もまた、背をシーツへと預ける。
視界に映る天蓋の模様が、今日はぼやけて見えた。
「また、あした」
歌うように紡ぐ約束の言葉。
こうして、ふたりの女の子は、お空へ旅立っていきました。
カーテンコールはありません。
ふたりの少女の87年間の公演は、これで終幕にございます――。
●
「……、……」
ヴェルグの墓前で短く黙祷し、空は再び旅に出る。
目指すは最果ての地。月の裏や火星、木製、土星の衛星――そこが人類未踏の地なら、片道の旅で良い。
探査機に乗って、データを送りつつ太陽系の外を目指すのも良い。人類にとって有益ならば、無碍にはされないだろう。
(「尤も、僕があと何年生きるかは、保証できないが」)
降り注ぐ太陽の光が眩しい。目を細めつつ、空は歳を重ねた身体を、足を動かす。
(「美幸はこの地獄を生き抜いてみせろ、と遺したけど」)
80過ぎても元気とは皮肉が過ぎる――口角を微かに上げた。
(「大切な人も先に逝った」)
長く生きるほどに失うのは希望、募るのは絶望。
この世は正に地獄だ……。
それでも、美幸の残滓の一片と共に、誰も見たことが無いような光景を、秘境をふたりで彷徨する人生は、そう悪いものではなかった――今ではそう思えるから。
だから最期も、静かにふたりで、と願う。
(「来世など多分無いけど」)
それでもひとかけらでもあるならば……そんな希望は捨てられない。
(「もし奇跡があるなら」)
今度こそ美幸、君と――。
●
一度目の死は、灼滅者として目覚めた13の夜だった。
謎の存在に襲われ、妹を守るために身体を投げ出した時。
結局、守ることは叶わずに、両親と妹はこの世を去り、清音だけが生き残った――死よりも辛い現実。
郊外の小さな家からは、時折ピアノの音が響く。手慰みで覚えたそれに合わせて紡がれる歌。
庭では花や野菜が育てられ、慎ましい生活が伺われた。
細々とした一人暮らし。それにもついに終焉が訪れる。
ある朝、いつものように太陽の光を感じたけれど、起き上がることはできなかった。
身体に力が入らないのに、感じるのは現実味のない浮遊感。
(「ああ――」)
それは『その時』が来たのだと悟るのに、十分すぎるものだった。
静かに、ゆっくりと瞼を閉じれば、浮かび上がるのはかつての大切な人の姿。
無意識に微笑みを浮かべていることに、そんな力が残っていたことに、清音自身は気がついていない。
「……ルナ……もうすぐ……、……そちらに逝くわ……また……、……会いましょう……」
紡いだ言葉が声となったのかはわからない。いいのだ、重要なのはそこではないのだから。
それはとある暖かい冬の日のことだった。
80を迎えた朝。
静かに微笑みながら、清音は人知れずこの世から旅立った。
●
88年後――104歳のアリス・ドールのベッドの周りには、家族や元教え子たちが集まっていた。このあとどこへ行くのか、それはドール自身が一番良く分かっている。
「……アリス……」
「……」
呼ばれ、ベッドサイドに膝をついたのは、アリス・フラグメント。
「……私は幸せ者でした。子、孫、そして曾孫のあなたに出会えたのですから……」
これが最期だと、誰よりも分かっているから、伝えたい。
「短い間でしたが、曾孫のあなたと学園生活を送れたのは……夢のような出来事でしたよ……」
「ひいお婆さま。わたしも、ひいお婆さまと一緒に過ごした武蔵坂学園は、楽しいことばかりでした。わたしの、一生の宝物です」
言い募るフラグメントの頬を、ドールは力の入らない手でそっと、撫でる。
「ありがとう……もう1人のアリス・ドール。あなたの物語とあなたが救った物語達が、ハッピーエンドになるように願ってますよ……」
撫でた彼女の指先が、いつもより冷たく感じる。フラグメントは、温めるかのようにその手をそっと握りしめた。
「ひいお婆さま、逝かないでください。まだ、お話したい物語が、思い出が、たくさんあるんです……」
フラグメントの言葉が届いたのかそれとも――ドールは穏やかに微笑んで。
「……あなた……お姉ちゃん……みんな……また……会えますね……」
声が言葉の形をとったかはわからない。
「……、……私は……幸せ……で……し……た……」
けれども、思いはかたちとなって――。
「ひいお婆さま……お婆さまぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ!!」
微笑みながら永遠の眠りについたドール。フラグメントが彼女に縋り付いて泣くのを、誰も止めはしない。
慟哭、慟哭、慟哭――涙は嗄れぬとばかりに、どのくらいそうしていただろうか。
ひとしきり泣いたあと、フラグメントは顔を上げた。そこには涙した痕跡がありありと残っていたけれども。
「ひいお婆さま、空のどこかで見ていてください」
語る言葉は強く、満ちるのは決意と誓い。
「わたしの……ひ孫『アリス・ドール』の物語を、ひいお婆さまに負けないくらいの物語をお見せします」
強き想いが、フラグメントを奮い立たせる――。
●
2100年――その夜、由衛は自宅にいた。
いつもと同じ夜。いつもと違うのは、己だ。
最早呼吸すら苦しい。その衰弱具合は、おそらく今眠れば、二度と目覚めることはないのだと確信できるほど。
そう自覚すると蘇るのは、90年近く遠い過去になってしまったあの頃の、数多くの輝く記憶。
長く長く、本当に長く長く歩み続けた道の中で、強く思い出されるもの。
走馬灯とは本当に見えるものなのか、などと頭のどこかで感心しつつ、そばに立つ『死』を思う。
(「死は『終わり』。可能性の停止で、変化の停止。終わって初めて題名のつく本、人生の完結」)
それでも、世界は進み続ける。想いは託されて、きっと、人々の未来は明るいと信じているから――。
「悔いは、ない」
紡いだそれは、本心だ。
(「ああ……」)
――思い出して欲しい。
嘗てそう語った影がいた。その思い出を胸に抱き、そして――世界への祈りをいだく。
目を閉じると、酷く楽だ。
手招きするのは、己の裡の影狐だろうか。共に沈みゆくのを感じる。
死の眠りへ、深く深く沈む――それで、終わり。
●
22世紀初頭、百十数歳を数えた琴弓は、布団に横たわっていた。夫には先立たれたが、その周囲には子どもをはじめ、玄孫はおろか来孫の姿もある。
大学卒業後、長年の想い人であった幼馴染と結ばれ、2男3女に恵まれた。
実家の甘味処を継いで、三号店まで事業を拡大した。
「ひなた、呆ける前に作った遺言状通りに、喧嘩のないようにね。店は随分前に皆に任せてるから、大丈夫だよね」
「結局、呆けてないじゃないの……」
てきぱきと指示をするその姿は、昔とちっとも変わっていない。長女はうっすらと涙を浮かべて小さく笑った。
「皆のおかげで楽しい100年でした。ありがとうね」
この世でやるべきことをすべて終えたというほどの、正に大往生。けれども皆が、あまりにも悲しそうな顔をするものだから、琴弓は決して悲しげな顔を見せず、泣きもしない。
「さて、そろそろ鷲ちゃんのところに向かう頃合いみたいだよ。皆はゆぅっくり来るんだよ、良いね」
言い含めるように告げて、瞳を閉じる。思ったより早く、皆の声が聞こえなくなった。迎えは、すぐそこまで来ていたのだ。
「あ、鷲ちゃん、迎えに来てくれたんだ」
在りし日の姿で愛しい人と、琴弓はゆく――。
| 作者:篁みゆ |
重傷:なし 死亡:なし 闇堕ち:なし |
|
|
種類:
 公開:2019年1月5日
難度:簡単
参加:33人
結果:成功!
|
||
|
得票:格好よかった 0/感動した 2/素敵だった 5/キャラが大事にされていた 10
|
||
|
あなたが購入した「複数ピンナップ(複数バトルピンナップ)」を、このシナリオの挿絵にして貰うよう、担当マスターに申請できます。
|
||
|
シナリオの通常参加者は、掲載されている「自分の顔アイコン」を変更できます。
|
||
