
クラブ同窓会~このほしを かけめぐる
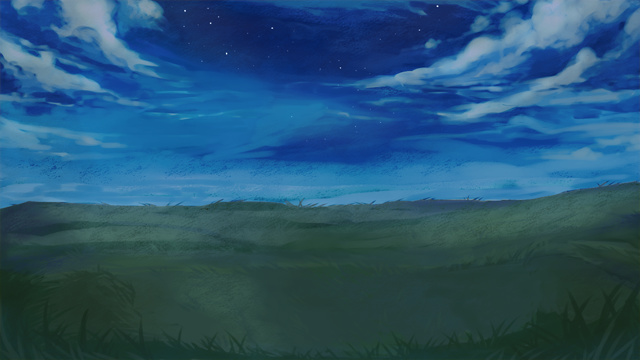


●2028年 南米ペルー
見渡すかぎりひろがる、砂の海。
ベージュと空色の境目をたしかめながら、砂漠の探検家――木嶋・キィン(あざみと砂獣・d04461)は慣れた足取りで砂山を登っていた。
まわりにはひと一人見あたらない。
眼前に壁のように立ちはだかる砂山を、ただただ、淡々と登りきって。
そこでようやく、これまで辿ってきた道を振りかえる。
――足跡の先に在るのは、オアシスをたたえた砂漠の街『ワカチナ』。
砂山からは、そのすべてを一望することができた。
沈みゆく夕陽を見やりながら、青年は山頂に腰をおろし、まぶしそうに眼を細める。
完全に陽が落ち、オアシスに次々と明かりが灯るのを見守って。
「あれからもう、10年か……」
過ぎ去った時の長さに、かつて学園で同じ時を過ごした者たちへ、想いをはせる。
たしか数少ない荷物のなかに、縁ある者たちの連絡先が残っていたはずだ。
ひとけのない、静かな砂漠も好ましいけれど。
だれかとともに過ごす時間は、それだけで贅沢なものだったと、あらためて感じて。
キィンは宝石のように瞬く星空を見あげながら、砂の夜の静寂に、身をゆだねた。
それから、しばらくして。
縁ある者たちのもとに、キィンから砂まじりの招待状が届いた。
オアシスの絵葉書一枚。
メッセージは、たった一行。
――砂漠の真っただ中に、星を眺めに来ないか?
■リプレイ
●
約束の日。
招待状を受け取った縁ある者たちは、まずは成田で3人が合流。
ニューヨークを経由し4人が合流した後、南米ペルーの首都、リマの国際空港に降り立った。
世界遺産ツアーに向かう人々を横目に、機上でこわばった身体を大きく伸ばすのは、一夜崎・一夜(エクスブレイン・dn0023)。
「『ワカチナ』は、地上絵のそばの土地だったのだな」
学生時代からのおかっぱ頭は、研究者として学園に所属するいまも健在。
ただし、学生時代のようにレディースファッションを取り入れた格好や化粧は、成人を機にやめている。
シンプルなシャツに、スラックス。
研究ざんまいで運動不足のくたびれた32歳には、長時間のフライトはこたえたらしい。
「ちじょう、え?」
隣にたたずむ、青白い髪にワンピース姿の小柄な女性――28歳になった七湖都・さかな(終の境界・dn0116)が、小首をかしげる。
いまだ言葉数はすくないものの、以前よりはスムーズに言葉を紡ぐようになり。
わずかばかり、表情も豊かになっている。
学生時代はロクに手入れをしていなかった髪は、今では丁寧にくしを通すようになった。
さらりと流れる背中までの髪を見ながら、
「二人とも、10年前の面影そのままに歳を重ねたようじゃの」
かつての頃を想い出し、同じく28歳のルティカ・パーキャット(黒い羊・d23647)が、感心したようにつぶやく。
なお、大学卒業後に日本国籍を取得したルティカは、姓を『架間(はさま)』と改めている。
名は変われど、往年と変わらぬ鮮明な赤の髪に、雪のように白い肌。
旅行内容にあわせてきたらしい、冒険家然とした格好が良く似あっている。
「白い七湖都と、赤い架間が並ぶと、実にいい絵になる」
とは、成田で再会した際の一夜の言だ。
「おー。サカナは知らねぇのか、『ナスカの地上絵』」
褐色の30歳男性、ケレイ・ザプトー(スタウロス・d03152)が投げかける。
ケレイは牧師見習いをしながら教会を建てているそうだが、今回はサーファーのような若々しいいで立ちだ。
ならぶ二人の身長差は、およそ30cm。
さかなはケレイを見あげ、「ん」と頷いた。
ニューヨークで出会ってからそれほど会話を交わしたわけではないが、互いに居心地は良いらしい。
「今から行く『イカ』経由で行けるし。明日あたり寄ってってみるか?」
「いきたい」
即答したさかなの視線を受け、一夜がにんまりと笑う。
「そんなこともあろうかと。あらかじめ、有休は多めに申請しておいた」
「そりゃイイネ」と笑ったケレイがバギーカーをレンタルして、ここからは車で次の街へ。
ただし、早くても4、5時間。
道路事情などによっては、7時間かかることもあるらしい。
とはいえ、心配ばかりしていても仕方ない。
助手席の一夜にナビゲーションを任せ、ケレイはルティカとさかなをエスコートすべく、始終、陽気な想い出話を語り続けた。
「ガクセーの頃は、キィンとアメリカ横断しようとかバカ言ってたなぁ」
「やっておることは、今とたいして変わらんようじゃが」
「横断、したの?」
「やった、やった! これがナカナカの珍道中でよ!」
聞いてくれよと後部座席の女性陣に顔を向けた瞬間、一夜が横からハンドルを押さえる。
「おい、こらザプトー! ちゃんと前をみて運転しろ!」
それから数時間。
一夜は始終、ケレイの運転にヒヤヒヤし通しで。
ルティカは、すっかり意気投合したさかなとケレイを微笑ましく見守っていた。
――元桜堤6組の賑やかさを思えば、大丈夫かの。
目を細め、愉快で気楽なドライブを楽しむ。
●
招待状にあった待ちあわせ場所。
夕暮れ前に『イカ』の街に到着し、ひと息。
「いいか。帰りはわたしが運転する。お前の運転は危なっかしくてかなわん」
「無事に着けたんだから、イイじゃねぇか」
「事故ってからでは遅いと言っているんだ!」
出会ってから、まだ一日も経っていない二人だったが。
遠慮なく言葉をなげあう様から、すっかりうち解けたらしい。
「ふたりとも、なかよし」
さかなとルティカが、くすくすと顔を見あわせて。
そのまま待機していると、ふいに、4人の前に人影が立った。
言いあいをしているケレイと一夜を見やり、
「……あの悪ガキは、なんで元サバイバル学部の2人にくっついて来てんだ?」
マントの下から無精髭を覗かせたのは、今回の引率役。
33歳になった木嶋・キィン(あざみと砂獣・d04461)だった。
気づいたケレイが、大仰にハグで出迎える。
「ダッハハ! モーセみてぇなツラんなってんぜ。すっかり探検家じゃねぇか、兄弟」
よく通る声で笑い、ばしばしとキィンの肩を叩く様子に、ルティカがフォローする。
「ケレイ殿は、ニューヨークでピックアップしてきての」
「実に、おまえの友人らしい友人だとわかった」
一夜は眉間に眉を寄せていたものの、
「久しいな、木嶋。今回は世話になるぞ」
久々の再会に、どちらともなく固い握手を交わす。
10年ぶりとはいっても、挨拶は昨日からの続きを思わせる気軽さだ。
「キィン。きた、よ」
一夜経由で受け取った絵ハガキを見せ、微笑するさかなの様子を見やり、「ああ」と頷く。
――変わったもの。変わらないもの。
「遠路はるばるようこそ」
ワカチナまでの案内は任せろと、ルティカ、さかなの荷物を引き受ける。
イカから『ワカチナ』までは、車で15分ほど。
その間にも太陽は地平線に近づき、視界いっぱいの広大な空が、大地が、すべてが赤く染まっていく。
「絶景だゼ!」
ヒュウと口笛を鳴らしたケレイが助手席から身を乗りだし、行く先を見やる。
「あれは、サボテン畑かのお」
「道路と砂しかない風景というのも、面白いものだな」
後部座席のルティカ、一夜も興味津々。
さかなは先ほどから窓に張りつき、流れていく電信柱を見送っている。
日本とおなじように、電柱が立っているのが不思議でたまらないらしい。
もちろん世界的な観光地なのだから、どこからか電気を引いているであろうことは、頭では理解しているのだけれど。
「オッ。見えてきたぜ!」
ケレイの示した方角に、一同が視線を移して。
現れたその光景に、目を見ひらく。
「水。あと、木も」
「まるで、絵に描いたようなオアシスじゃのお。街が夕暮れに浮かぶようなのも、不思議な光景じゃな」
「砂中に急に現れたなら、夢と思うのも無理はないな」
訪問者それぞれの反応を見守りながら、キィンは街中へ車を進める。
確保していた宿へ案内すると、「すぐに出かけるぞ」と、準備を促した。
改めて宿前に集まった4人を見渡し、キィンが説明を開始する。
「帰り時は」
と、茜と紺が混ざりあう空を指さし、
「――あの目立つ橙色の星が、あの辺りまで動いたら」
「要するに、フィーリングということか」
ツッコミを入れたのは一夜だけで、ほかの3人はそのまま受けとったらしい。
「オアシスの位置を見失いさえしなければ、帰りはどうとでもなるかのお」
「まあ、道程は心配するな」
ルティカの声にキィンが請けあったところで、ケレイが言った。
「せっかくだから、オレ滑ってくるわ」
聞けば早々に準備を整え、先にサンドバギーとサンドボードのレンタルを済ませておいたらしい。
「ケリー。歩け」
「あ? 歩け? しゃーねーなぁ」
話半分、わしわしと頭をかいて。
「イチヤもどうだ?」
「いいだろう。そのかわり、勝負しろ。私が勝ったなら、帰りの運転は私がする」
「オッケー、オッケー」
この数時間で、ケレイは一夜のあしらい方を覚えたようだ。
「じゃあ、オレたちは滑りまくって満足したら、テキトーなところで合流するわ。サンドボードに乗りながらでも、星は見れるからな」
パイプフレームの無骨なサンドバギーに、ボードと荷物を積みこんで。
「ヒャッホー!」と声をあげたケレイが、勢いよくアクセルを踏みこむ。
――ザプトーぉぉおお!!!!
砂の壁を勢いよく駆けあがるバギーから、一夜の悲鳴が尾を引いて響く。
不思議そうに見やるさかなに、キィンが言った。
「砂山は、道が整備されていないだろう。だから見た目以上にアップダウンがあってな。天然のジェットコースター体験ができるぞ」
「ケレイ殿の運転なら、さぞ刺激的なドライブになるじゃろうて」
そんなところだと、キィンが笑って。
「オレたちも出発するか」
砂に足をとられやすいから気をつけろよと促し、オアシスを背に、歩き出した。
●
キィン、ルティカ、さかなの3人は、一歩一歩、しっかりと砂を踏みしめながら進んで行った。
「我もさかな殿も、しっかり日焼け対策をせねば後が辛そうじゃが。遅い時間の出なれば、大丈夫であろうか」
夜の風は冷たいと聞いていたので、上着を身につけてはいたのだが。
日焼け対策となると、普段程度にしかしていない。
「明日も歩くなら、気をつけた方が良いだろうな」と、キィンが応えて。
「砂漠の生き物も日中なら見られるんだが、またそのうちな」
「生き物。いるの?」
食いついたさかなに、キィンが頷く。
「いるとも。ここはオアシスもあるから、生きやすい」
こんな砂漠でも、季節はめぐっていて。
ひとも生き物も。
土地土地の恵みを享受しながら、いのちの限りを生きている。
砂山を登りきるころには、すっかり日も沈んでしまった。
快晴の夜空には月が煌々と輝いており、振りかえれば、夜闇にワカチナが浮かびあがっているのが見える。
砂丘の頂上から見る夜のオアシスには光があふれ、人々の営みを感じるようで。
「あたたかい、ね」
物心ついたころから、さかなは日本でくらした記憶しかない。
北欧から日本へ渡ったルティカにしても、この光景はどの土地とも違って見えている事だろう。
自分にとっての、「あたりまえ」の風景。
それが、ここにはなにひとつ存在せず。
ここでうまれた者たちにとっては、このすべてが、「あたりまえ」として映る。
手元あかり用にとキィンがオイルランプに灯をともせば、ようやく互いの顔が見えるようになった。
「キィンは。どうして、あちこち旅、してるの?」
さかなが、そう問いかけた時だ。
サーチライトを思わせるバギーのヘッドライトが、遠くからまっすぐに砂丘を照らすのが見えた。
キィンがカンテラを振り、こちらの位置を示す。
「Yeahー! ようやく見つけたゼ!」
ケレイの声とともに、駆けつけたバギーが3人の前に滑りこんできた。
助手席でうなだれている一夜を見るに、勝負はついたのだろう。
「おい、木嶋……。こいつの体力は、底なしか?」
車から降りた一夜は、ぐったりと砂の上に座りこんで。
「否定はしない」
「体力オバケになんぞ勝てるか!」
叫ぶなり、大の字になって砂の上に転がった。
「一夜崎、大丈夫かー」
覗きこめば、どうやら一夜は一瞬のうちに眠りこんでしまったらしい。
さかながそばに座りこみ、寝息を確認して、頷く。
「一夜、このところ徹夜続きで。昨日も寝てなかったって」
飛行機で仮眠をとりつつ、同窓会テンションでここまで来たが。
全力で遊んだおかげで、体力が尽きたのだろう。
「まるでスイッチの切れたこどものようじゃな。身体が冷えぬよう上着でもかけて、眠らせておくがよかろうて」
ルティカの言葉に、ケレイが車に積んでいた荷物から一夜のジャケットを放り投げる。
「ヤレヤレ。世話の焼けるオトナだな」
「まったくだな、ケリー」
キィンが深く頷き、血のつながらない兄弟を見やる。
さかなは一夜のそばに座りこみながら、夜空を仰いだ。
空に向かって、手を伸べるようにして。
それから、ぱたり、背中から砂に身を委ねる。
「どれ。我も横になってみるかの」
ルティカがさかなのとなりに腰をおろし、友を真似てぱたりと倒れた。
キィン、ケレイも、一同に倣って。
5人、頭で円を描くようにして、砂に身体を預ける。
視界いっぱいにひろがった空には、月光にも負けぬ輝きをもつ星々が瞬いている。
「北欧の星空は木々に遮られるで、此処は圧巻であるな」
「ん。ここの星は、村から見るどこの空ともちがう」
ルティカの言葉に、さかなが頷く。
「じゃが、抱えられそうなほど在っても、一つも手に届かぬのは此処も同じか」
さかなが先ほどそうしたように。
ルティカも、天に手を伸べたことがある。
「届かぬ方が、いつまでも追いかけられるのやもしれぬが――」
「嬢ちゃんたちが普段見てる空も、オレが見てる空も。今見てるモンと同じなんだけどよ。キレーじゃねえか、なぁ」
踏みしめる大地があって、空がある。
五体満足の身体があって、友がいる。
それで良いのだと、ケレイは笑って。
「綺麗なものに、どうして目がいくんだろうな。あるいは、心が動いたものが美しく見えるのか」
旅をしていると、あらゆる『きれいなもの』に触れる機会がある。
夜空に浮かぶ月や星。
沈む夕陽。
霧がかった、朝の砂漠の空気。
力強く根づく草木。
羽根ひろげた鳥のシルエット。
「長く居るとな、わかってくるんだ。砂丘の個性とか風の兆しとか、星の動きだとか」
見えなかったものが、視えてくる。
その感動が、キィンの心を震わせる。
――いまをいきていると、感じる。
語るキィンの言葉に、さかなは、先ほどへの問いかけの答えを見つけたような気がして。
そっと、自分の胸に手を当てる。
「カンパイでもしようや。いつもは摩天楼に隠れて見えない、お星サンを肴によ」
起きあがり、ケレイが街で調達しておいたという、酒瓶を並べはじめる。
「しんみりするよりは、騒いでおる方が我ららしいか。――ケレイ殿、其れを我にも」
そうとなれば、ルティカに続いて、キィンとさかなも起きあがって。
「「「「乾杯」」」」
眠りこんだ一夜が目を覚ましたのは。
4人の酒瓶が、空になるころだった。
●
残りわずかの酒を恵んでもらい、一夜も夜空と酒を満喫したころ。
件の『橙色の星』が、ようやく予定していた位置に至った。
軽くなった酒瓶をバギーに積み直し、オアシスへ帰る準備に入る。
話題は、自然と次の同窓会の話に移った。
「次の招待状は、何処から届くのやら」
我も北欧へ赴く時があるやもしれぬから、連絡先はしっかり把握しておかねばの、とルティカが笑えば、
「オレはここに暫く滞在して、次はタクラマカン砂漠、その後はサハラ」
「気ままな旅暮らしか。うらやましいことだ」
つぶやいた一夜に、キィンが続ける。
「今からでも、一緒に行くか?」
問われ、一夜は即答した。
「いいや。私は、あそこで。ヒトとダークネスに関わり続けていくのだと、決めたからな」
それは、一夜が学生時代から抱えてきた、ある誓いへの答えでもあって。
予想通りの言葉に、「そんなところだろうと思った」と、キィンが肩をすくめる。
「七湖都は、あの村に移住したんだったか」
問われ、さかなは「ん」と頷く。
「あの村のゆくさきを、見届けたいって。そう、おもえたから」
学園へ来た当初。
帰る家も、故郷も喪ったさかなにとっての居場所は、保護者代わりである一夜のそばしかなかった。
そんな少女が「村に行く」と決断できるまでに成長できたのは、ひとえに、学園で暮らし、仲間と過ごした時間があったからだ。
「今もこうしていつでも会えるし、懐かしがるほどフケてもねぇ」
新しいダチも増えたことだし、また楽しみが増えたなと、ケレイが白い歯を見せる。
「ああ。脚が続く限りひた走って駆けぬいたら、いつかは還るよ」
「気長に待つとしようかの」
笑いあう3人を見やって。
一夜とさかなも、顔を見あわせて、笑った。
ケレイがレンタルしたバギーは、あいにく4人乗りで。
だれかひとりを置いていくわけにもいかず、3人が乗車し、2人が歩いて帰ることになった。
行きにケレイの天然ジェットコースターを体験した一夜は、サンドバギーはもうこりごりと、乗車を辞退。
「おー、イチヤ。それならサンドボードで競争しながら、イッショに帰るか?」
「それこそお断りだ!」
そんなわけで。
バギーの運転はケレイに任せ、女性陣2人が、ひとあし早くオアシスへ帰ることに。
なにしろ彼女たちには、『一日の砂を落とす』という、やっかいで重大な作業が待っているのだ。
「すまぬが、先に戻らせてもらうでな」
「キィン。一夜のこと、よろしくね」
「任された」
和やかに挨拶をかわす3人のとなりでは、
「いいか、ザプトー。くれぐれも安全運転だからな。行きの10分の1のスピードで走れよ」
「わかった、わかった。イチヤは途中で寝オチしねぇようにな」
かくして。
バギーを見送った夜の砂漠に、男二人。
オアシスまで歩くには、まだいくらか距離があって。
「行くか」
先行くキィンの足跡を、一夜が踏みしめるように歩く。
サンドボードを置いていってもらえば良かったかとぼやくも、後の祭りで。
キィンはそんな一夜を見て、再会時から気づいていたことを、言った。
「くだけたな」
その言葉に、一夜はニッと、口の端をもたげた。
「こっちの方が、ニンゲンらしいだろ」
それは、ようやく。
ヒトであることを受け入れられたのだと、告げるようで。
「ちがいない」
キィンは静かに肯定し。
かつての戦友とならび、星の下を、歩きつづけた。
| 作者:西東西 |
重傷:なし 死亡:なし 闇堕ち:なし |
|
|
種類:
 公開:2018年11月23日
難度:簡単
参加:3人
結果:成功!
|
||
|
得票:格好よかった 0/感動した 0/素敵だった 7/キャラが大事にされていた 0
|
||
|
あなたが購入した「複数ピンナップ(複数バトルピンナップ)」を、このシナリオの挿絵にして貰うよう、担当マスターに申請できます。
|
||
|
シナリオの通常参加者は、掲載されている「自分の顔アイコン」を変更できます。
|
||
